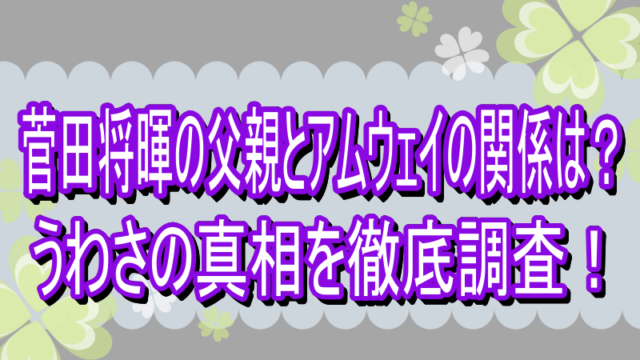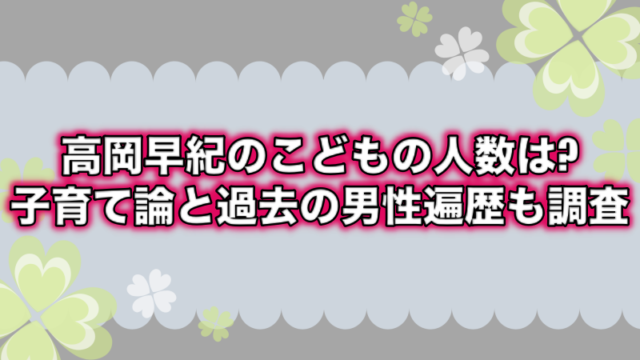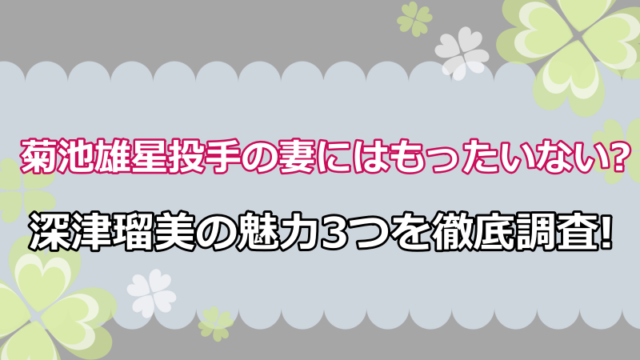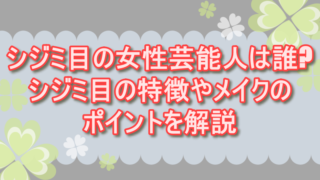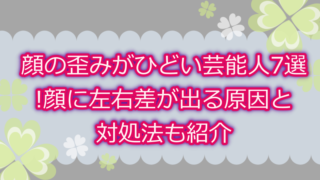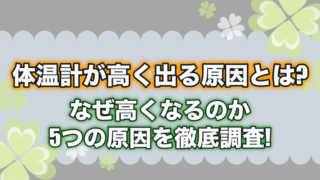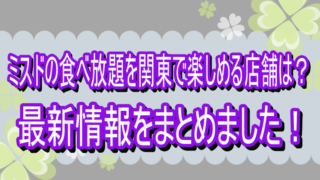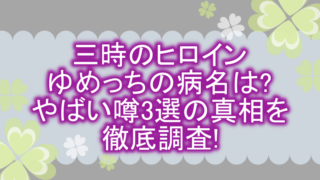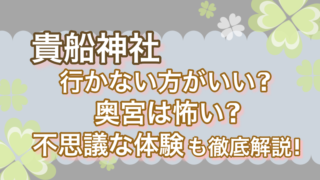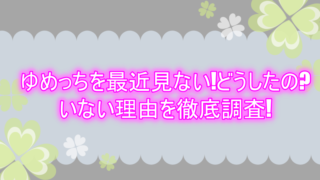そしてバトンは渡されたの映画版はひどい?泣けない理由を徹底分析!
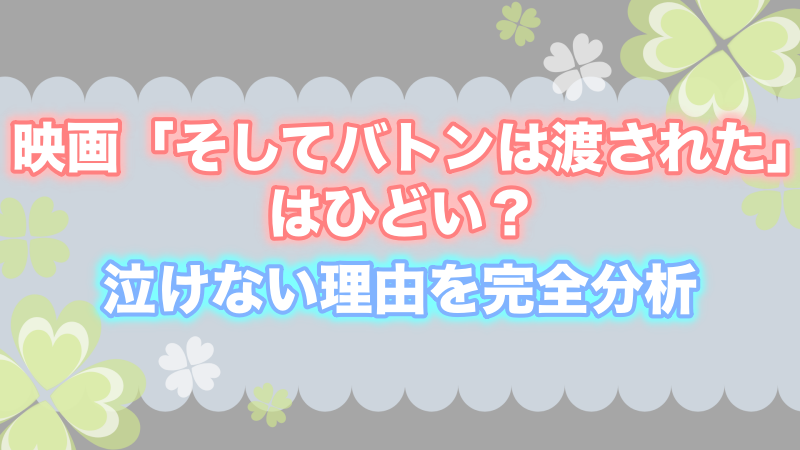
映画「そして、バトンは渡された」を鑑賞し、「なぜ泣けないのだろう」と感じたあなた。
あなたは、決して冷たい人間ではありません。
「泣ける映画」として宣伝された本作。
ですが脚本や倫理観の矛盾に違和感を覚えたとしても不思議ではありません。
それは、登場人物の心情を想像できるからこその違和感だからです。
この記事では、「ひどい」と言われる要因を分析していきます。
Contents
そしてバトンは渡されたの映画版がひどいと言われる3つの問題
多くの観客が涙する一方で、一部から批判されるのには理由があります。
物語の土台となる論理や倫理観に、矛盾や問題があるからです。
ここでは、指摘の多い3つの問題点を解説します。
①死の隠蔽が生む不快感
物語では梨花の死を優子に隠し結婚式の直前に伝えるという展開です。
しかし、この死に目に会えない事や幸せな結婚前に伝える事に違和感を感じます。
これは物語の核心となる「梨花の死」にまつわる展開ですが…
感動を呼ぶどころか、嫌悪感を引き起こす要因となっています。
梨花が自らの病を隠し通す理由として「親の死を2回も体験させたくない」「自由な梨花はどこかで楽しく生きていると思っていて欲しい」という心情が語られます。
「死を体験させたくない」という願い。
これは「死に目に会えない」悲しみと後悔を娘に植え付けることになります。
娘を想う親心のように聞こえますが、冷静に考えると残酷で理解に苦しみます。
この秘密によって、優子は育ての親との「別れの機会」を奪われてしまいました。
さらに批判が集まるのは、優子が結婚報告をするタイミングで、義父の泉ヶ原から梨花の死を知らされる展開です。
結婚式の直前に、報告されるのは、「最悪のタイミング」と言わざるを得ません。
この展開は、優子にとって「悪趣味なドッキリ」を仕掛けられたのと同じ。
優子や現在の父である森宮さんは、この不誠実に対して激怒してもおかしくありません。
作中ではその怒りが描かれることなく、感動的なシーンとされています。
観客は登場人物の感情に違和感を覚えます。
②父親たちの聖人化による人間味の欠如
映画に登場する父親たちは、物語を円滑に進めるために都合よく動く「舞台装置」のよう。
人間らしい葛藤や負の感情が欠けているように描かれています。
最初の父親である水戸は、家族に相談もなくブラジル移住を決め、会社を辞めてしまいます。また、梨花も幼い娘を残して突然姿を消します。
現実的に見れば、「自分勝手」や「育児放棄」と非難されるべき行動です。
映画では身勝手な行動がすべて「優子のため」「愛ゆえの決断」と美談にされています。
「子供を押しつけて逃げた」としか見えない行動。
これを愛の物語として正当化しようとする脚本に対し、不快感を抱くのは当然の反応です。
3番目の父親である森宮さんも、梨花が突然消えてしまったにもかかわらず、何の文句も言わずに優子を育て続ける「いい人」として描かれています。
本作の登場人物は、「善人」ばかりです。
裏切られたり理不尽な目に遭ったりしても、誰も怒らず、恨み言も言いません。
負の感情が見えない彼らは、人間としてのリアリティがありません。
物語を成立させるための「都合の良い駒」に見えてしまいます。
「いい人しか出てこない」という構造が、不気味さや嘘くささを生んでいるのでしょう。
③ラストのバトン演出に見る古い結婚観
タイトルを回収するラストシーンの演出も、現代の価値観とはかけ離れています。
これには拒否反応を示す観客が少なくありません。
結婚式で、父親たちがリレーのようにバトンを渡し、最後に新郎へ渡すという演出。
娘を「親が所有し、夫へ渡す所有物」のように扱っている印象を与えます。
このシーンは感動のクライマックスとして描かれています。
「娘はバトンなのか?」「優子はモノ扱いなのか」
という反発を招いたこのシーンは、古い結婚観を思い起こさせます。
女性の主体性を無視されたかのような描写。
これに「気持ち悪かった」という感想を抱くのは、健全な感覚です。
そしてバトンは渡されたの映画版における違和感の正体は映画独自の3つの過剰な改変

「脚本の粗」の多くは、原作小説には存在しません。
映画化にあたって追加・変更された点にあります。
映画独自の改変がどのように物語を歪めてしまったのかを解説していきます。
①梨花は死んでいない
映画と原作の大きな違いは、梨花の生死です。
この改変こそが、物語全体のつじつまを崩す元となっています。
原作小説において、梨花は病気を患ってはいるものの、死んではいません。
優子は2番目の父・泉ヶ原から居場所を教えられ、梨花と再会を果たし、結婚式にも参列しています。
映画版で梨花を病死させた理由。
これは短時間で観客の涙を誘うための「悲劇の演出」であると思われます。
「死なせた方が泣けるだろう」という意図が見え隠れしてます。
結果として「映画を盛り上げるために命が軽く扱われている」という批判を招くことに。
原作が持っていた「生きて関係を修復する複雑な愛」。
これが「死によるお涙ちょうだい」へと単純化されてしまったのです。
映画では「親の死を2回も体験させたくない」という理屈で梨花に姿を消させましたが、これは原作にはない映画オリジナルの設定です。
この理屈のせいで優子は「死に目にも会えない」という結末を迎えることになります。
生きていれば対話ができます。
しかし映画では死なせてしまったため、梨花の真意は手紙などで知るしかありません。
感動を優先するための「死」の演出。
これが物語としての品格を落としてしてしまったと言えるでしょう。
②みぃたん呼びと過度な幼児性
主人公・優子の幼少期を「みぃたん」と呼ぶ設定も、映画独自のものです。
これがキャラクターの魅力を損なっています。
原作には「みぃたん」という愛称は登場しません。映画では、梨花が「みぃみぃ泣くから」という理由で名付けたと説明され、すぐに泣く感情的な子供として描かれています。
原作の優子は知的な子供。
映画の中の「お米もうないよ」と家計を心配するシーンがあります。
このように本来の彼女は経済状況を冷静に見つめる、大人びた子供でした。
映画版は、あえて優子を、「可哀想で幼い子供」として演出した可能性があります。
それが優子の本来持っていた聡明さを消してしまっています。
映画では、家の隅で泣く優子の姿を強調するなど、観客の保護本能を刺激するために「可哀想な子供」を演出。
高校生になっても「辛い時こそ笑う」という教えを守り、常にニコニコしている描写は、健気さを通り越して不気味にさえ映ります。
「泣かせ」や「同情」を得る演出は、「あざとい」と受け取られ、感情移入を邪魔します。
優子が周りに翻弄されるだけの存在に見えてしまいます。
彼女の芯の強さが伝わらなくなってしまったのは、大きなマイナス面でしょう。
③心理描写のカットと泣かせの優先
映画は2時間という枠に収めるため、登場人物の心の揺れ動きをカットしてしまいました。
感動の結末へ向かう葛藤を飛ばしてクライマックスへ急ぐ構成で物語を進めていきます。
親が変わるたびに生じるはずの葛藤や、距離が縮まっていくプロセスが、映画では描かれていません。
話し合いや生活の現実といった「間」が省かれているため、出来事すべてが唐突に映ります
その象徴が卒業式のシーン。
原作とは異なる合唱曲を使用し、森宮さんが号泣する姿を見せる。
そこで「ここは泣くところです」と誘導させるような演出になっています。
積み重ねがないまま、音楽と演技だけで感情のピークを作ろうとする。
これは「感動の押し売り」であり、観客が白けてしまう原因です。
そしてバトンは渡されたの映画版はなぜこんな脚本に?制作背景にある大人の事情3点

原作の良さを消してまで、なぜ強引な脚本になったのでしょうか。
そこには映画製作特有の事情が見え隠れします。
①短時間で泣かせる分かりやすい悲劇
原作は、淡々とした日常の積み重ねや、血の繋がらない家族の微妙なニュアンスが描かれています。
製作者側は、これらが多くの観客に伝わるか不安だったのではないでしょうか。
興行収入を確保するためには、誰が見ても分かりやすく、感情を揺さぶる要素が必要です。
結果、原作の「生存」という設定を変更。
「病死」というドラマチックで悲劇を生む選択がなされました。
物語の繊細さや誠実さよりも…
「泣ける映画」としての分かりやすさを優先したこと。
これがこの脚本を生んだ原因と言えるでしょう。
②ミステリー要素・サプライズの過剰演出
映画は、幼少期と高校時代の2つの物語を並行させています。
最後にそれらが繋がる「サプライズ」の構成になっています。
この仕掛けを成立させるために、時系列をいじり、情報を隠す必要が生じました。
その結果…
キャラクターの行動原理(なぜその時そうしたのか)のつじつまが犠牲になっています。
「伏線を回収する快感」を優先するあまり登場人物の動機やプロセスの描写がおろそかに。
物語全体が不自然なつぎはぎになってしまったのです。
③感動大作というマーケティング
「鑑賞者の9割が泣いた」という宣伝コピー。
これが示すとおり、「泣ける映画」として売り出されました。
この「泣かせ」のマーケティング。
これは観客に対して「泣けない自分はおかしいのではないか」という圧を与えます。
演出によって感情のレールを敷かれ、「さあ、ここで泣いてください」と迫られると…
自然に湧き上がる感動を失います。
結果として、感受性が豊かで論理的な人ほど、冷めた目でスクリーンを見つめることに。
そしてバトンは渡されたの映画版で冷めた人こそ原作を読むべき3つの理由
(2026/02/01 16:33:25時点 楽天市場調べ-詳細)
映画版にがっかりした人こそ、ぜひ原作小説(瀬尾まいこ著)を手に取っていただきたい!
そこには、映画で感じた不満を解消する「本来の物語」があります。
①すべての行動に納得できる理由がある
映画で感じた「なぜ?」という疑問の答えが、原作に用意されています。
「梨花の生存」はもちろん、なぜ優子を置いていったのか、行動の裏にある愛情と複雑さが描かれています。
映画の不自然な展開は、すべてオリジナル要素。
「そうだったのか」と納得できるはずです。
②押し付けがましくない静かな肯定感
原作は、「泣け!」と迫ってくるような作品ではありません。
日々の食事や会話、森宮さんのぎこちない優しさなどが積み重なり、じわじわと心が温まる物語です。
血の繋がらない親子が、本当の家族になっていく過程が描かれています。
読んだ後は号泣ではなく、心地よい感動に包まれるでしょう。
③モヤモヤが晴れる快感
映画を見て、梨花や父親たちのことを「身勝手だ」などと感じていたなら、勿体ないことです。
原作を読むことで、そのネガティブな印象は上書きされます。
ラストの「バトン」演出も、原作では異なるニュアンスで描かれています。
そこに不快感はありません。
映画によって歪められた登場人物たちの名誉を回復。
物語が本来持っている、優しさと愛の形を受け取ることができます。
まとめ
- 梨花の死の隠蔽の理由や聖人化された父達がリアリティを欠如している
- バトン演出における古い結婚観がひどいと感じる原因
- 梨花は死んでいない事や優子の過度の幼稚性など過剰な改編がみられる。
- 泣かせ優先で心理描写がないことが違和感に。
そしてバトンは渡されたの映画版では梨花の死や父達のリアリティ欠如、古い結婚観など…
過度な改編の内容が多く、見る人にとっては「ひどい」作品と感じられることもあります。
映画は商業的な成功を優先するあまり、物語のつじつまが犠牲になってしまいました。
しかし原作小説は素晴らしい名作です!
原作には誠実な愛と、あなたを納得させるだけの深みがあります。
ぜひこの物語が本来伝えたかったメッセージを受け取ってください。