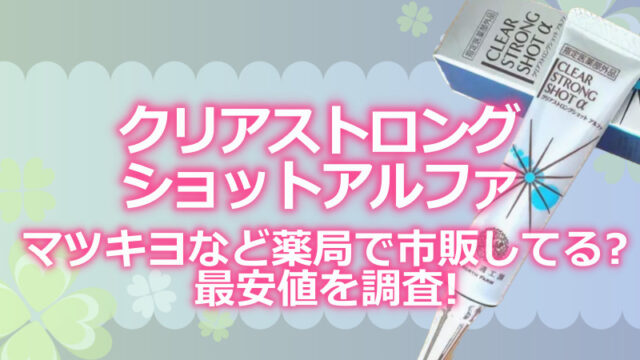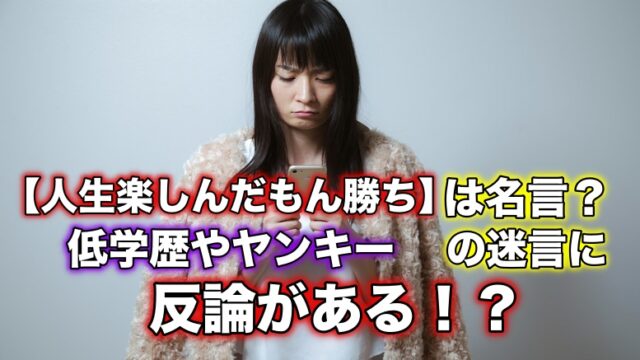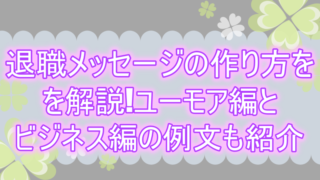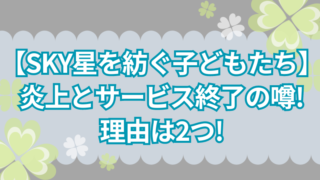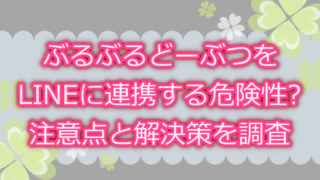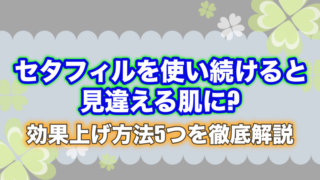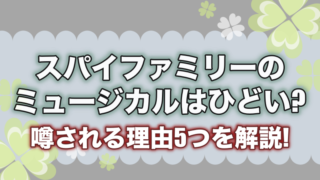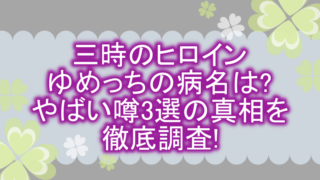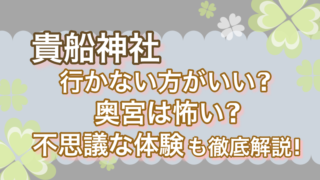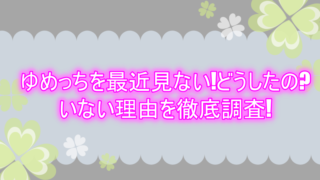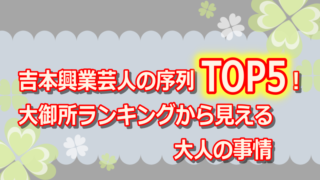ラグビーのハカはずるい?ハカが認められている理由と歴史を徹底調査
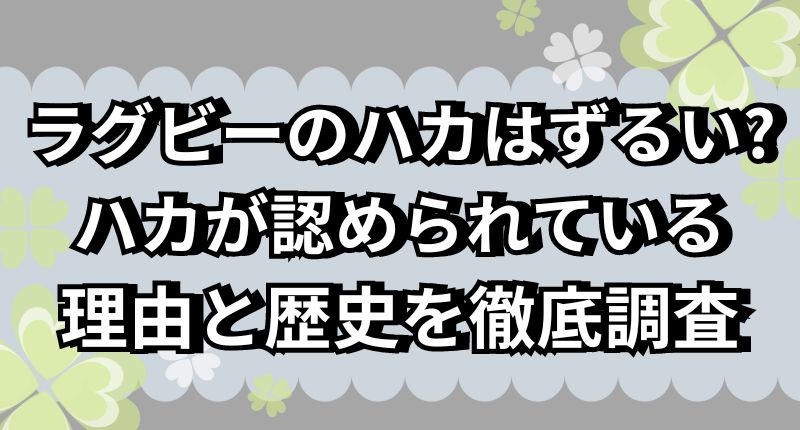
ハカといえば、ニュージーランドの原住民マオリ族が、戦いの前に行う儀式。
特にラグビーにおいて、ニュージーランドのナショナルチーム「オールブラックス」が試合前に披露することでも有名です。
そのハカが、ネットで「ずるい」と言われているというのです。
なぜハカが「ずるい」と言われているのでしょうか?
今回はラグビーのハカについて詳しく調べてみました。
Contents
ラグビーのハカが「ずるい」と言われる理由

X(旧Twitter)で調べてみたところ、「ハカはずるい」という声は確かにありました。
全力のハカはずるいな
— けい (@idol_gayter) January 14, 2020
さらに調べてみると、その「ずるい」には2種類の意味があるようです。
- かっこいいからずるい
- 優遇されていてずるい
賛否両論ありますね。
それぞれの意味について深堀りしてみました。
①かっこいいからずるい
いい意味では、「かっこよくてずるい」という声がありました。
オールブラックスのハカには、毎回釘付けになるファンが多いようです。
ハカというものがラグビーの見世物なんかではなくて、ニュージーランドのマオリ民族の伝統的な民族舞踊ていうのがずるいくらいカッコいいhttps://t.co/RQMAXfDxm5
— ながどん (@takuya_nagaaai) October 12, 2019
オールブラックスは世界最強レベルのくせにハカとかいう独自の超かっこいいパフォーマンス(神聖な踊りをパフォーマンスとか言うな)持っててずるい
— ゼノ (@Yu_rashia) October 12, 2019
真っ黒のユニフォームに、戦士の表情で繰り出すハカは確かにかっこいいです。
民族の誇りが感じられるところもいいですよね!
②優遇されていてずるい
オールブラックスだけハカを披露する時間があって「ずるい」という意見がみられました。
「日本チームも何かパフォーマンスをすればいいのに」という声も。
ラグビーワールドカップ、ニュージーランドだけがハカの時間があるのがずるい。
いつか日本も「高砂」で返信できるようになって欲しい。 pic.twitter.com/jqB1qssY71— 電脳玩具職人そーご (@s0g0project_s) September 21, 2019
ラグビーW杯、ニュージーランドとかだけハカやるのちょっとずるいから日本も15人全員でかめはめ波やらない????絶対圧倒出来るって!!!!!!!
— 今日のむいむい (@mui_king) October 3, 2019
しかし屈強のラガーマンがかめはめ波をしたら、全世界のアニメファンから「日本人ずるい」と言われそうですね。
オールブラックスだけ優遇?ハカの定義とルール

「ずるい」と言われているハカですが、ニュージーランドのハカだけが優遇されているわけではありません。
キックオフ前のパフォーマンスについて、ラグビーの国際競技連盟・ワールドラグビーの記述を調べてみました。
ハカの定義
多様性を尊重するワールドラグビーは、ハカを「文化的挑戦」と定義しました。
挑戦(Challenges)は、相手チームに対する宣戦布告とも少数民族のチームに課された課題とも解釈されています。
Respect for kickers, injured players, cultural challenges and remembering the greats of the game no longer with us.
(キッカーや負傷した選手、文化的挑戦、この世を去った選手への追悼に敬意を示すこと)
スポーツでは、ケガで離脱した選手に声援を送ったり、亡くなった選手に黙祷を捧げたりする時間がありますよね。
文化的挑戦の時間もそういった時間と同じように敬意を示すべきものと考えられています。
ハカのような「文化的挑戦」をするチームは、オールブラックスだけではありません。
ミクロネシアの国々には、名前は違いますがハカによく似たパフォーマンスがあります。
- シピタウ(トンガ)
- シヴァタウ(サモア)
- シビ(フィジー) など
もちろん、これらのチームのパフォーマンスも「文化的挑戦」として認められています。
ニュージーランド対トンガなどミクロネシア同士の対戦の際は、パフォーマンスの応酬も見られるとか!
次に文化的挑戦について解説します。
文化的挑戦のルール
文化的挑戦にはちゃんとルールがあります。
ワールドラグビーによれば、両チームが文化的挑戦を行う場合とどちらか一方が文化的挑戦を行う場合について、こんなルールがあります!
- 一方はハーフウェイラインを超えないところまで出る
- もう一方は10メートルラインより後ろにいなければならない
- 双方の位置はコイントスで決める
- パフォーマンス中のチームは自チームの10メートルラインを越えてはならない
- 挑戦を受けるチームは、自チームのハーフウェイラインを越えてはならない
- 挑戦を受けるチームは、それに直面する必要はない
といったルールが決められています。
パフォーマンスを行っている間、両チームは少なくとも10メートル離れていなくてはいけません。
過去にハカのパフォーマンスを妨害するような行為が何度かあり、それによるトラブルを防ぐためとも考えられます。
違反した場合は、ペナルティが課されることも。
2019年のワールドカップで、イングランド代表がV字の陣形を組んでオールブラックスに向き合いました。
V字の両端がハーフウェイラインを越えたため、イングランド代表は罰金の支払いを言い渡されたのです。
文化的とはいえ、ハカは威圧感のあるパフォーマンスです。
相手チームもひるむことなく対抗しようと思ったのかもしれません。
ハカにこめられた意味

威嚇と取られがちなハカですが、必ずしも好戦的な意味があるわけではありません。
ハカの起源については、マオリ族の間でこんな伝説が残っています。
マオリの伝説によると、ハカは生命の祝福として始まったということです。
太陽神タマ・ヌイ・テ・ラとその妻、夏の神ヒネ・ラウマティには、タネ・ロレという名の息子がいました。
夏の暑い日には、タネ・ロレは母親のために踊り、それが熱気を震わせるのだそうです。軽快で素早いその動きは、すべてのハカの基礎となっています。
祝福の踊りが元になっているのですね!
現代のハカには、大きく分けて2つの意味があります。
- 士気を上げる
- 敬意を示す
それぞれの意味を解説していきますね!
①士気を上げる
ニュージーランドでは、ラグビーに限らずあらゆるスポーツで選手たちがハカを踊ります。
士気を上げるために足を踏み鳴らし、マオリ語の歌で鼓舞するのです。
ハカという名前が浸透する前は、ウォークライ(戦の前や勝利した時に上げる雄たけび)と呼ばれていました。
オールブラックスが試合前に行う定番のハカ「カマテ」の歌詞の意味を見てみましょう。
私は死ぬ!私は死ぬ!
私は生きる!私は生きる!
私は死ぬ!私は死ぬ!
私は生きる!私は生きる!
ここに毛深い男が立ち
太陽を呼びよせ、我が身のその光を
乗るなら今だ!乗るなら今だ!
最初の一歩を踏み出せ!
太陽の光を!
立ち上がれ!
目を剥く、舌を出すなどの表情は相手を威嚇しているように見えます。
しかしその歌詞には、相手を傷つけるような意味はありません。
スポーツだけでなく、選挙や議会の演説の場でも披露されます。
命を懸けて戦う、といった決意表明の意味があるのですね!
②敬意を示す
卒業式や追悼式などさまざまな行事で行われるハカもあります。
2016年に紹介された、結婚式でのハカは世界中で話題になりました。
新郎ベンジャミンさんと新婦アーリヤさんを祝って、新郎の兄弟と友人が披露したハカです。
途中から新郎が参加し、美しく着飾った女性たちも歌い出しました♪
最後には、涙ながらに見ていた新婦も加わった感動的な一幕です。
まさに生命を祝福する踊りですね♪
まとめ
- ネットの声は「かっこよくてずるい」と「優遇されていてずるい」
- ハカは「文化的挑戦」と定義され、ルールも存在する
- ハカの起源は生命を祝福する踊り
- スポーツのハカには士気を上げる意味がある
- 結婚式などで、敬意を示すためにも踊られる
「ずるい」と思うほどかっこいいハカ。
込められた意味を知って、また違った目線でラグビーを見られそうです!