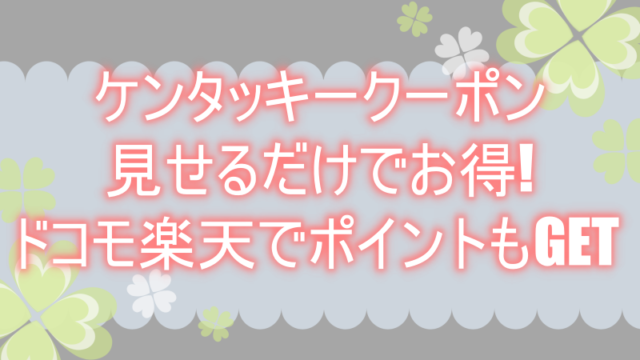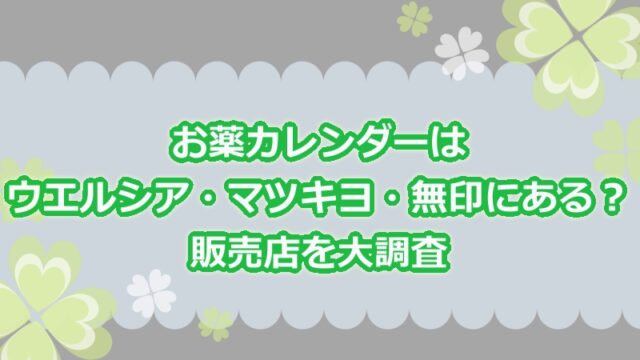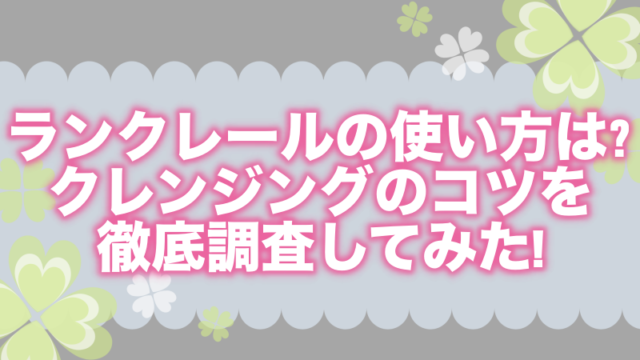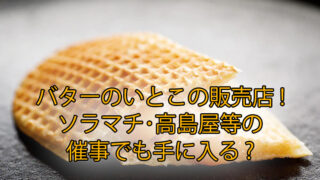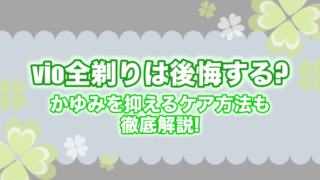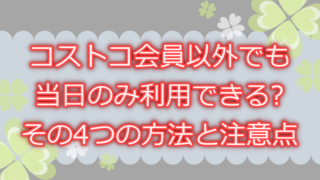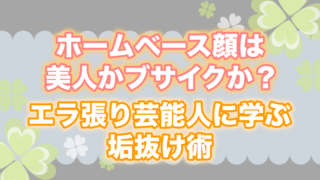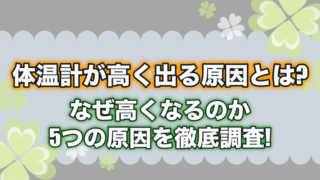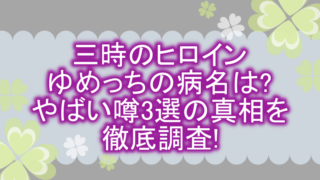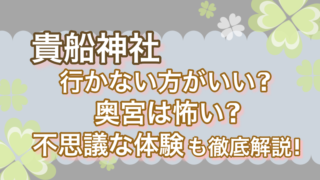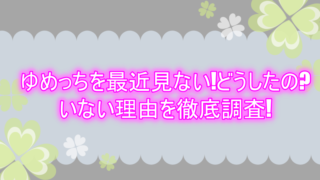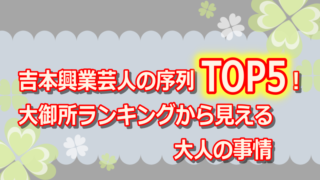修正テープの直し方!たるみや出てこないときの対処方法を徹底調査!
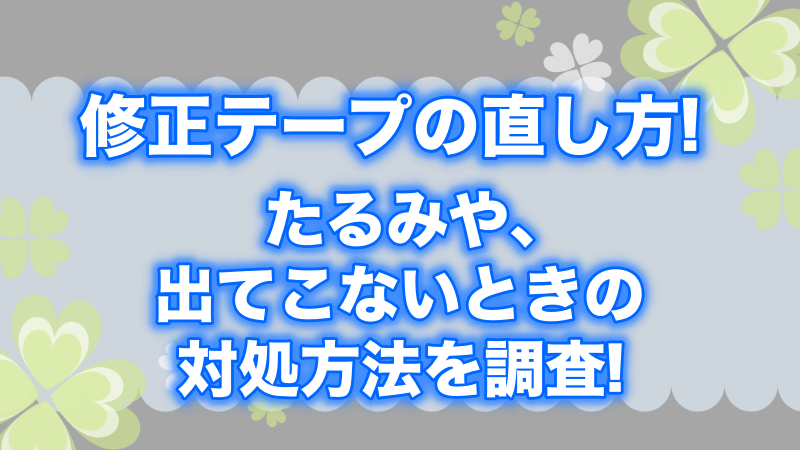
修正テープはビジネスや勉強に欠かせない便利アイテム。
筆者も長らく愛用しています。
ホワイト修正ペンのように乾くのを待つ必要もなく、修正面もフラットできれいです。
でも過去にはテープがたるみ、直し方がわからず悪戦苦闘したことも。
ほかにも、テープが出てこない!といったトラブルに見舞われる人も多いそう。
そこで、そんな不測の事態の対処方法や原因などを探ってみました。
修正テープ愛用派にありがちなお悩みに、解決のお役に立てれば幸いです!
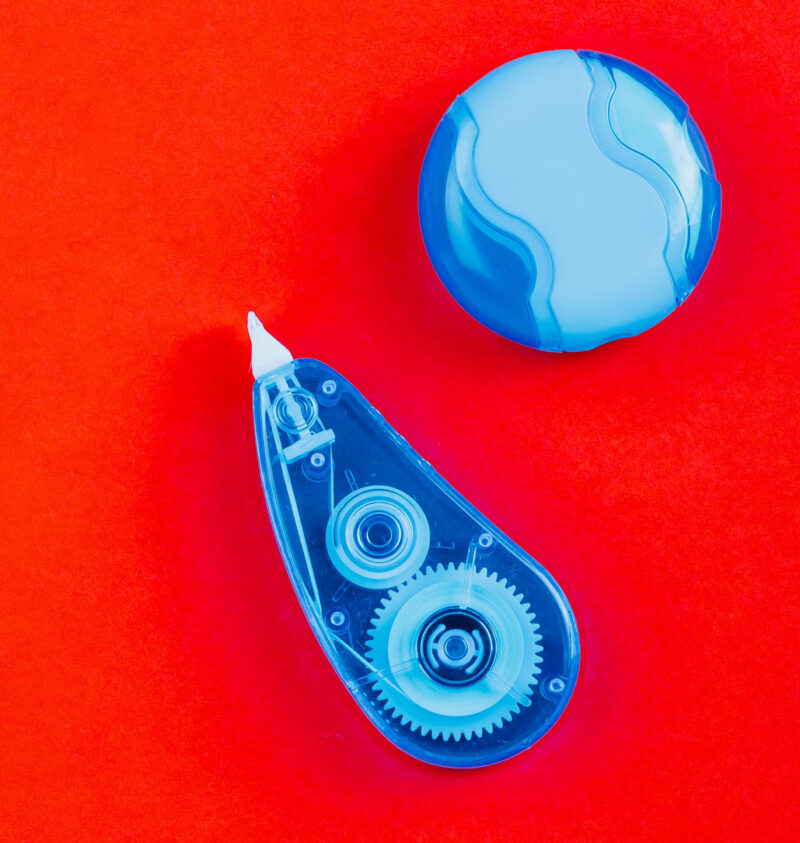
Contents
修正テープの直し方!たるみやねじれを取る方法
修正テープユーザーで多いのが、使っているうちにテープがたるんでしまうことではないでしょうか。
たるみの直し方は主に2つ。
「テープを引き出して巻き直す」
「修正テープの本体を開けて巻き直す」
これでほとんど解消できます!
- テープを外に少し引き出す
- 引き出したテープを指でピンと張った状態にする
- 巻き戻しボタンや巻取り穴で巻き戻し
- ボタンや穴がない物は、ローラーの穴にペンなどを差し込み、巻き戻す
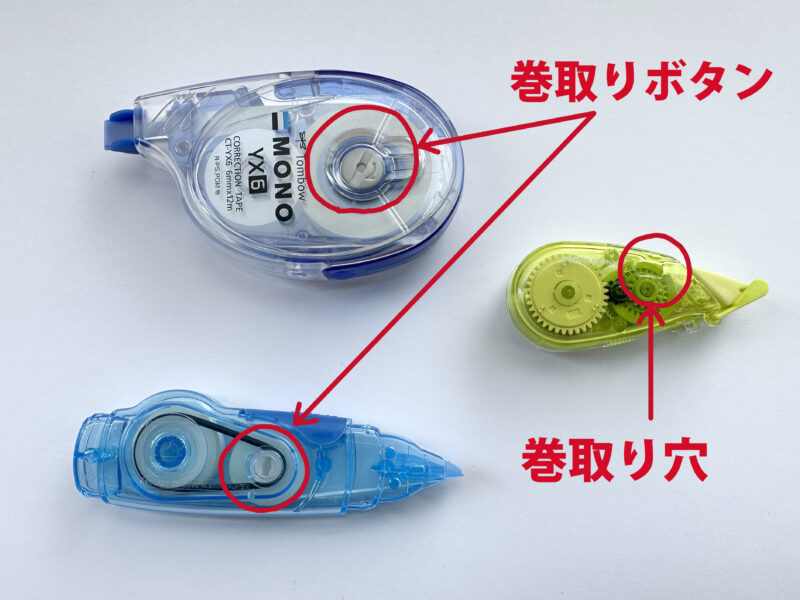 機種により巻取り方法が違う
機種により巻取り方法が違う
たるんだ上にねじれているときは…
ねじれを伴う場合は、ケースを開ける必要があります。
このとき細かい部品を落とすなど、過度にバラけないよう用心しましょう!
- ヘッドのキャップをはずす
- 本体ケースを開ける。ドライバーなどを差し込んで開けてもよい
- 前側のロール(使用済みのテープを巻き取る方のロール)を取り外す
- 必要に応じてヘッド部分を取り外す(写真の機種は構造上必要なし)
- テープのねじれを直す
- テープを元通りかけ、上蓋を閉じる。外したキャップも装着

元通り組み立てたら、何度か引いてみて調整しましょう。
後述しますが、組み直し後に動作トラブルが起きることもあります。
順番など間違えないよう注意しましょう。
修正テープが出てこない場合はどうしたら良い?
 SNSなどでは「テープが出てこない」という声が多いようです。
SNSなどでは「テープが出てこない」という声が多いようです。
原因はさまざまですが、主に次のようなことが考えられます。
- 中でテープが絡まっている
- テープが切れている
- 立てる角度が適切でない(直角過ぎる、または寝かせすぎている)
- 縦引きのものを横に引いている(あるいはその逆)
- 引くときの圧力が強すぎる
- 組み立て直したら出なくなってしまった
分解には要注意!バラす前にスクショしよう
多く見受けられたのが「分解したものを組み立て直したらテープが出なくなってしまった」というもの。
テープが出てこない原因の中の「1.テープの絡まり」と「2.切断」については本体ケースを開けて直す必要があります。ねじれを伴うたるみ修正の際も同様です。
実際にバラしてみるとわかりますが、修正テープの構造って意外と複雑です。
組み上げ方を間違えるとうまく動かなくなってしまうんです。
そして部品が小さい。したがって、とても失くしやすいのも注意点です。
どうにか手だけで復元はできたものの、不器用な筆者にはピンセットが必要だと思いました。
 ↑特に最小の黒い歯車など、飛んでいってしまったら見つかりません…
↑特に最小の黒い歯車など、飛んでいってしまったら見つかりません…
慌ててフタを開ける前に、出来上がり画像をスクショするのがおすすめです!
 筆者は3個組を持っているため実物をお手本にしました!
筆者は3個組を持っているため実物をお手本にしました!
筆者はお手本になる同じ製品があったのでどうにかなりましたが、あまり細かくバラすのはおすすめしません。
もちろん、不可抗力でバラバラになってしまった場合は仕方がありませんが…。
部品の位置、テープの回し方など覚えるのはたいへん。
分解は必要最低限に留めましょう!
参考動画
以下に、組み直しの際に参考になりそうな動画を紹介します。
メーカーにより違いがあるのでこれがすべてではないのですが、大まかに構造をとらえるのには役立つと思います。
この動画で使っているのはプラスのホワイパーシリーズのようです。
↓ 修正テープの機構・構造の考え方がよくわかる動画
「修正テープを組み立ててみた」
https://www.youtube.com/watch?v=EW3uUc7-rTA
修正テープはどんなものが良い?商品選びのポイント5つ!
調べていると、トラブルが多いのは主に100均で買ったものが多いみたい…
文具店で扱うメーカー品は、使用感も安定していると感じます。
値段は4〜500円からくらいしますが、長く使うなら専門メーカー品の購入がおすすめです。
100均製品にもメーカー品はあるのですが、安いのにはそれなりの理由があります。
コストを抑えるために、雑な作りになってしまいがちです。
上記で紹介した、たるみ防止機能の他にも製品を選ぶポイントはいくつかあります。
- 縦引きタイプ or 横引きタイプ
- カートリッジ式 or 使い切り式
- ヘッドカバーのタイプ
- テープの幅
- 本体のサイズ・形
使いやすさは人それぞれですので、用途に合わせフィットするものを選んでくださいね。
①縦引きタイプ or 横引きタイプ
文字通り、縦引きは縦書きに、横引は横書きの修正に適した形になっています。
別に縦横逆でも使えないわけではありません。そして、どちらも一長一短があります。
筆者は縦引き派ですが、横書きの修正で不自由を感じたことはありません。
②カートリッジ式 or 使い切り式
修正テープには、カートリッジを詰め替えるタイプもあります。
お気に入りの本体を使い続けたい人におすすめです。
使い切りタイプに多いのは、小型のものや100均で売られているもの。
手軽に使えるところがよいですね。
③ヘッドカバーのタイプ
ヘッドに何もついていないものから、カバー式、スライド式、キャップ式などがあります。持ち歩くなら何かしら、カバーできるものが安心です。
④テープの幅
各メーカーで、細いものは2.5mmから太めの10mmなどが揃います。
一般的なのは5〜6mmで、本体の選択肢もよりどりみどり。
目的に合わせて選んでくださいね。
⑤本体のサイズ・形
デスクに置きっぱなしなら大きくても良いですし、持ち歩きが主ならペンケースに入るミニサイズのものを。小型タイプにはペン型の細長いものもあります。
修正テープを上手く使うためのポイント4つ
忙しいときにいきなりトラブるのは、本当に困りますよね。
各メーカーで修正テープを上手く使える方法をホームページなどで紹介しています。
共通しているのは
- テープと紙を密着させ、均等な力で引く
- 本体を立てる角度に注意(45度くらいの角度がベスト)
- まっすぐ直線に引くこと。曲線を描くと切れることもあります
- 平面上で使用する
などですね。
各メーカーの公式サイトやYoutubeなどの参考動画もあります。
ぜひ参考にしてみてください。
パイロットの公式サイトhttps://www.pilot.co.jp/support/revision/1297051949490.html
シードの公式サイト「修正テープの使い方のポイント」
http://www.seedr.co.jp/tape/tape3.html
まとめ
- たるみの直し方はおもに2つ
- 組み立て方を間違うと出てこなくなる
- 修正テープは小型ながら複雑な構造。分解するときは出来上がりをスクショしてからかかると安心
- 購入時は、なるべく文具専門メーカーの製品を選ぶ
- 正しい使い方をすれば、トラブルは少ない
今回、実際に修正テープの分解をしてみました。
そこでわかったのは、修正テープは小さいけれど緻密な機構を持つ道具だということ。
メーカーの方の工夫や、真剣に作られていることが感じられました。
丁寧に扱い、正しい使い方に則ること。それがトラブルを避ける一番の方法だと思います!