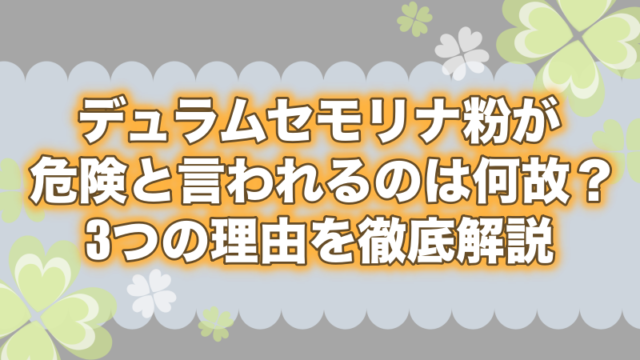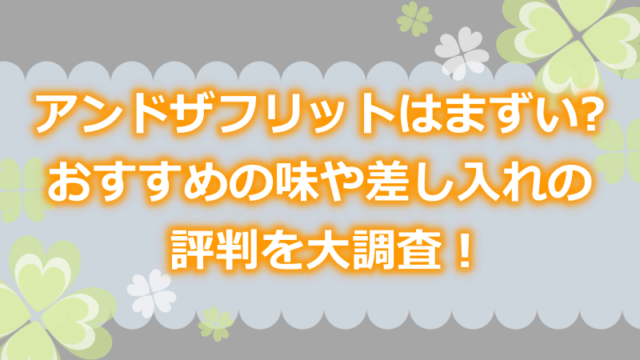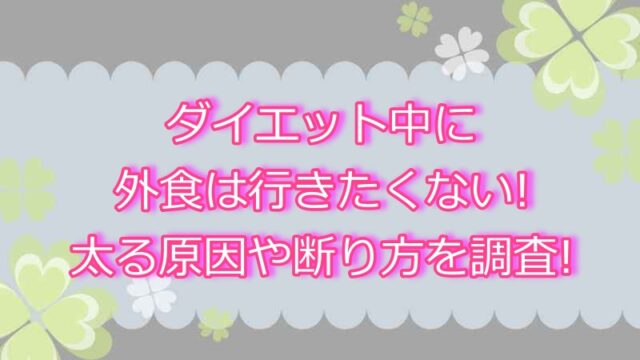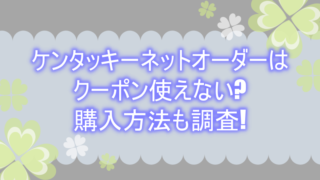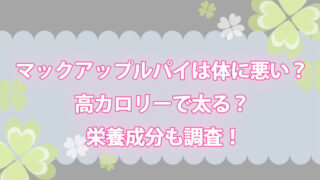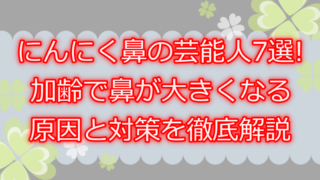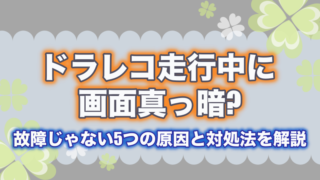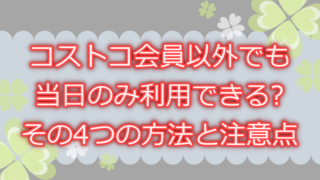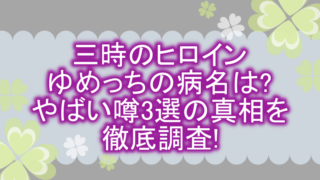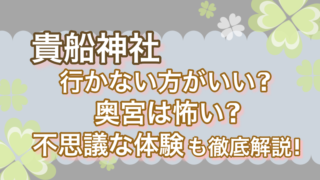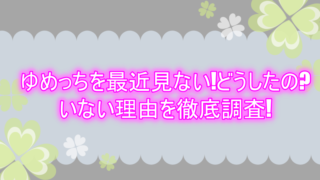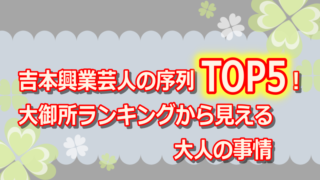おにぎらずの包み方4つ!パタパタたたむコツなどを徹底調査してみた
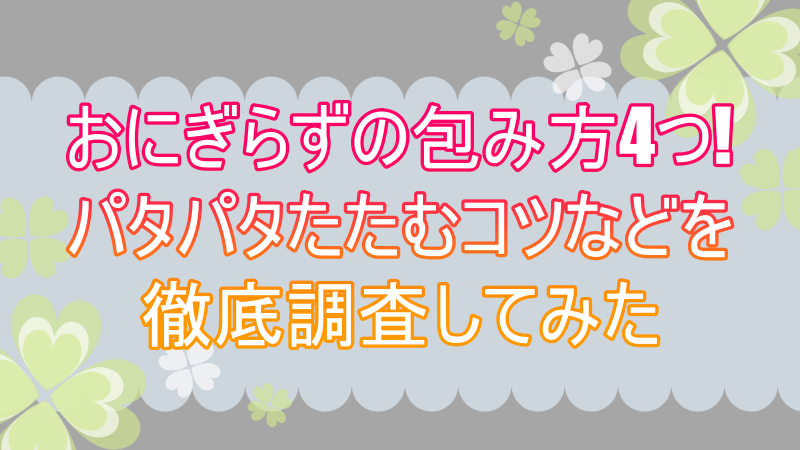
食べやすくて見た目も華やかなおにぎらず。
作ってみたいけど、難しいのかな?
と思っている方もいるのではないでしょうか。
おにぎらずの包み方は、実はいろいろあるんです。
どんな種類があるのか?
また最近話題になったパタパタおにぎらずとはどんなものなのか?
これらを順番にご紹介したいと思います!
おにぎりに似ているけど、意外と奥が深いおにぎらず。
具の入れ方や海苔の包み方、カットする向き、傷みにくい作り方など…
おいしく綺麗なおにぎらずを作るためのコツもぜひ参考にしてみてください!
Contents
おにぎらずの包み方4種類
おにぎらずの包み方は、定番の物はもちろんアイデアや工夫をこらしたものまでいくつもあるのをご存じでしょうか?
- 1枚の板海苔をひし形に置く。
真ん中にご飯、具材、ご飯の順に重ねて置き、海苔の四つ角を真ん中に持って来て包む。
おにぎらずの発祥はこの形と言われている。 - 上の包み方のアップデート版。
3個組の豆腐の容器を利用してご飯、具材、ご飯と詰めて海苔の真ん中に置くという方法。
この方法だと形が崩れにくく綺麗な四角形が作りやすくなる。 - 小さいサイズで作りたい時は、海苔を半分にカットしたり手巻きずし用の海苔を使う。
長方形の海苔の半分にご飯と具を置きパタッとたたんだり、真ん中にご飯と具材を乗せたら両側から真ん中に向かって包むやり方もある。
半分に切ったらミニサイズのおにぎらずの出来上がり。
お子様のお弁当などにも良い。 - 板海苔の下半分に切り込みを入れてパタパタと折りたたんで作る折りたたみおにぎらず。斬新な作り方で楽しく、見映えもするため大人気。
また、間に海苔の層が入ることで複数の具を入れても崩れにくく、作りやすさも食べやすさも兼ね備えている。
おにぎらずに決まりはないので、いろいろ試してみると他にも作りやすい方法が発見できるかもしれませんね!
おにぎらずのパタパタ折りたたみ方!コツも解説

上でもご紹介した折りたたみおにぎらず。簡単に楽しく作れて断面もきれいなので、挑戦してみたいという人も多いのではないでしょうか?
1枚の海苔を4つの区画に分けてご飯や具をそれぞれ乗せていき、下の片側からスタートして上→横→下とパタパタと進んでいくのが一般的な作り方です。
4区画のうちの1、2カ所にご飯を乗せ、残りの区画に具材を乗せる方法が多いです。
「そぼろ等のこぼれやすい具材はご飯の上にあらかじめ乗せておく」
「最初の1区画は何も乗せずに海苔で次の具材を押さえる」
などがうまく作るコツになります!
工夫すると、より作りやすくなりますよ♪
断面がどうなるか順番を考えながら作ることと、パタパタ折りたたみながら手でぎゅっと形を整えて最後にラップできつめに包んでなじませることも大事なポイントです!
おにぎらずの綺麗な断面を作る3つのコツ

映える断面のおにぎらずを作るためのコツを3つご紹介します!
1.色味を考えて複数の具を入れる
ほうれん草(緑色)と揚げ物(茶色)、卵焼き(黄色)とハム(ピンク)など彩りの良い複数の具を入れることで、見た目も味もぐっとアップします。
とは言え、たくさん入れすぎると具がはみ出たり海苔が破れたりしてしまうので、3種類程度までにするのが作りやすくておすすめです♪
2.切った時にきれいに見える具を選ぶ
オクラ・ウインナー・千切りの野菜・卵など断面のきれいな具を使うことで、真ん中で切った時にきれいなおにぎらずが完成します。
出来上がりを想像しながら、彩りよく配置するのも楽しいですよね!
3.切る方向を間違えない
ラップに包み終えたら切るところに輪ゴムをはめておくことで、切る方向を間違えるミスを防げます!
せっかく具の種類や並べ方に気を配っても、縦横を間違えて切ってしまったら断面が残念なことに…。
輪ゴムをはめるだけなら簡単なので手軽ですよね。
よかったら試してみてください♪
おにぎらずの傷みやすい具材や気を付けるべきことは?
気温が高くなる季節。おにぎらずの具材や作り方によっては傷みやすくなることもあります。
レタスやきゅうりなどの生の野菜は彩りに便利でつい入れたくなりますが、時間がたつと水分が出やすく傷みの原因になります。
緑色が欲しい時は、ほうれん草やピーマンなどを調理して使うと安心ですね。
また、ご飯や具が温かいうちにラップで包むと内側に蒸気がたまって傷みやすくなるため、しっかり冷ましてから包むことも大切です。
保冷剤なども上手く使いながら、夏場でもおいしいおにぎらずを楽しめるといいですね!
まとめ
- おにぎらずの包み方は主に4種類あるが、アイデア次第でやり方はいろいろ
- パタパタおにぎらずは、1枚の海苔を4区画に分けて順番にたたんでいく
- きれいな断面を作るコツは、彩りを考えて複数の具材を乗せること
- 夏場は特に水分の出にくい具材や冷ましたご飯を使い、傷まないよう気を付ける
以上、おにぎらずの包み方や話題のパタパタおにぎらずの作り方、きれいに作るコツなどについてまとめてみました。
おいしくて見た目もきれいなおにぎらず、ぜひ挑戦してみてくださいね♪