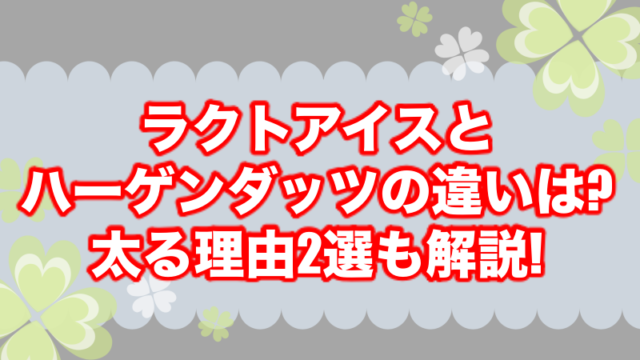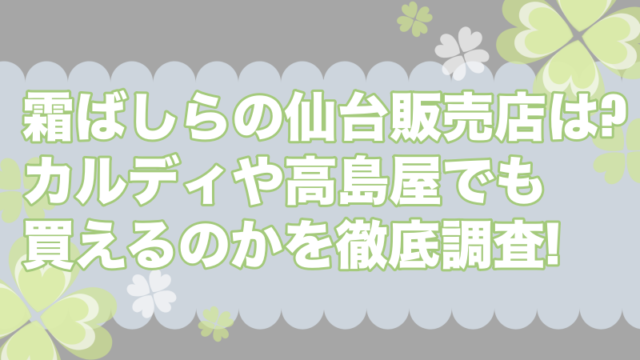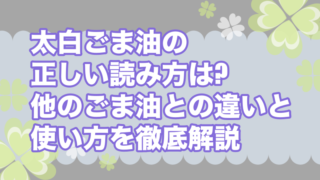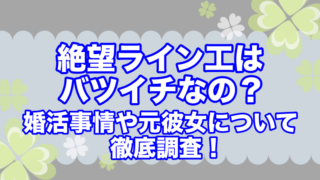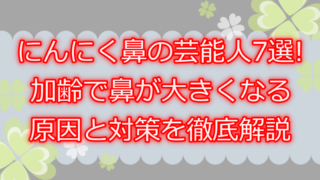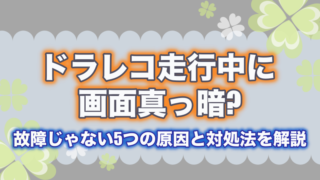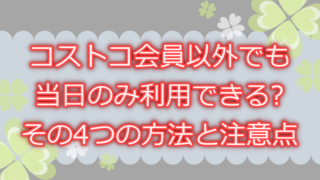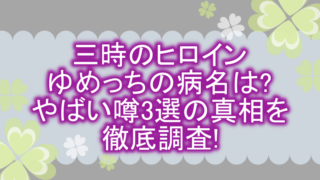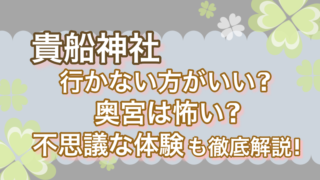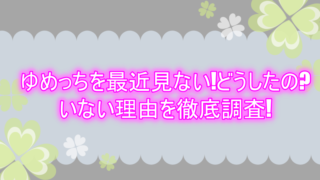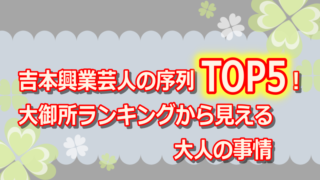ぬか床の作り方は?ためしてガッテンで放送したコツと活用法を紹介!
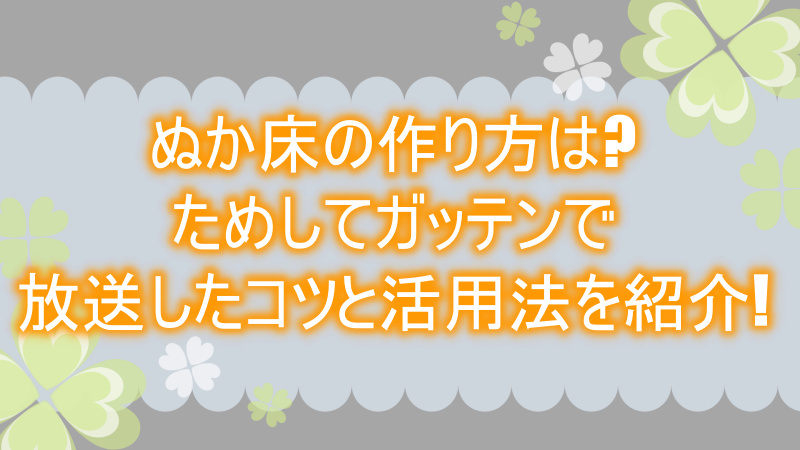
ぬか漬けは、発酵食品で身体によく美味しいですよね。
市販のぬか漬けも良いですが、自分で漬けたものは格別!
ただし、ぬか漬けを作るにはぬか床が必要です。
意外とぬか床の作り方を知らない人も多いのではないでしょうか。
今回は、以前NHKの「ためしてガッテン」という番組で紹介していたぬか床の作り方をご紹介します!
さらに、ぬか床の活用法や古漬けの再利用法もまとめました♪
是非最後まで読んでくださいね。
Contents
ぬか床の作り方【ためしてガッテン流】
ぬか漬け(ためしてガッテン流) | 糠床の作り方・栄養・すっぱい https://t.co/xZuplDRjHC
— アフロさん (@aflokarin1) June 28, 2022
2008年6月18日放送回「植物性乳酸菌の恵み!ぬか漬け・達人の極意」でぬか漬けについて紹介されていました。
ためしてガッテンで紹介されたぬか床の作り方は以下のとおりです。
- 米ぬか・塩・水を合わせて練る
- うまみ付け・捨て漬け用の野菜を漬ける
- 1日2回かき混ぜる
- 捨て漬け野菜を取り出し新たな野菜を漬ける
詳しく作り方のポイントをまとめたので、ご覧ください!
①米ぬか・塩・水を合わせて練る
ぬか床は米ぬか、塩、水を混ぜて作るのが基本の作り方です。
米ぬかkgに対して1.2リットルの水を鍋に入れて火にかけて沸騰させます。
塩(粗塩が望ましい)を入れて煮溶かし、火を止めて置いて粗熱をとっておきましょう。
別の鍋にぬかを入れ、弱火で炒ります。
薄いきつね色になってきたら火を止め、粗熱を取りましょう。
漬物容器にぬかを入れ、粗熱をとった塩水を少しずつ加えて混ぜていきます。
漬物容器で混ぜにくい場合は、大きなボウルなどの別な容器に入れて混ぜると作業がしやすいです。
②うまみ付け・捨て漬け用の野菜を漬ける
保存性を高めたり、風味を足す意味で唐辛子や昆布をぬかに混ぜ込みます。
お好みでゆず皮なども入れると風味が変わるため、おすすめです♪
いきなり食べる野菜を漬けるわけではなく、最初は捨て漬け用の野菜を漬けます。
野菜くずでいいので、にんじんや白菜、キャベツの芯や茎の部分などを埋めて漬けましょう。
最後は手で空気を抜きながら、表面を平らにならします。
ふたやラップなどで覆い、冷暗所で保管しましょう。
捨て漬けをすると、ぬかの塩分が均一になって味がまろやかになる、ぬかの発酵を助ける、などの効果があります。
「捨て漬け」はとても塩辛いため、食べられません。
③1日2回かき混ぜる
ぬかを熟成させます。
7~10日間ほど、朝夕の1日2回を目安にぬか床をかき混ぜましょう。
空気を入れるように、上下を入れ替えるようにかき混ぜるとよいです。
こうすることで、ぬか床の乳酸菌が増えることにより、熟成されていきます。
④捨て漬け野菜を取り出し新たな野菜を漬ける
捨て漬け用の野菜に付いているぬかをぬぐいながら、野菜を取り出します。
取り出したら、野菜を絞って絞り汁も加えましょう。
捨て漬け用野菜を新たに加え、再度漬けます。
1日2回かき混ぜ、7~10日間続けることを繰り返してください。
捨て漬け用野菜を2回漬けることで、ぬかの熟成が進み、ぬか床らしい芳醇な香りがしてきます。
これでようやく、ぬか床の完成です♪
ぬか床のお手入れポイント4つ

美味しいぬか床が作れても、手入れを怠っては台無しです。
ここでは、毎日のぬか床のお手入れポイントを詳しく解説します♪
- 毎日ぬかの上下を入れ替える
- 空気を抜いて乳酸菌をとじこめる
- ぬか床がにおってきたら
- ぬか床の最適温度は25度
①毎日ぬかの上下を入れ替える
1日1~2回を目安に、上下を入れ替えるようにかき混ぜてください。
空気に触れている部分と触れていない部分を「入れ替える」のが大事です。
ただ、ぐちゃぐちゃとやみくもに混ぜすぎると、空気が入って乳酸菌が減ってしまいます。
美味しいぬか床をキープするために、混ぜ方のポイントを抑えましょう♪
②空気を抜いて乳酸菌をとじこめる
ぬか漬けの美味しさの決め手は「乳酸菌」です。
かき混ぜた後は、ぬか床を押して空気を抜くことで、乳酸菌のはたらきを高めることができます。
乳酸菌は空気を嫌う性質があるため、混ぜすぎは厳禁!
ぬか漬けのうまみは、乳酸菌によって野菜を発酵させることでつくられます。
乳酸菌が減ってしまうと、ぬか漬けが美味しくないどころか雑菌が増える原因に…
乳酸菌が出す乳酸は酸性のため、雑菌の繁殖を抑えます。
③ぬか床がにおってきたら
乳酸菌は、増えすぎても減りすぎてもいけません。
ぬか床には乳酸菌や酪酸菌などの菌がいます。
このどちらかが増えすぎても、ぬか床が臭う原因となってしまうので注意しましょう!
「蒸れた靴下のにおい」がするときは、酪酸菌が増えた合図です。
こんなときは、米ぬかと塩を足しましょう。
こうすることで、におい物質の濃度が薄まります。
表面にうっすらと白い膜が張るまで寝かせたら、「上下を入れ替えて混ぜる」を何度か繰り返してください!
④ぬか床の最適温度は25度
ぬか床は温かい季節に作るのがおすすめ。
ぬか床が良い具合に発酵して、美味しくなります♪
25度が最適温度、と覚えておきましょう。
でも、夏場の暑すぎる時期はぬか床が発酵しすぎてしまいます。
室温が30度を超えるようであれば、冷蔵庫で保存してくださいね!
ぬか床の食べ方・古漬けの活用方法3つ

ためしてガッテンでは、ぬか床の食べ方や漬かりすぎた古漬けの活用方法も紹介していました。
ぬか床を食べるなんてびっくりですが、とても美味しいのだとか!
実際に紹介されていた3つを、詳しく解説します!
- ぬかみそ炊き
- 古漬けの炒め物
- 古漬けのサラダ
ぜひ、参考にしてくださいね。
①ぬかみそ炊き
北九州の小倉に住んでる知人がぬかみそ炊きを送ってくれました♪ぬかみそ炊きと言うのは小倉の郷土料理でさばやイワシなどの青背の魚をぬか漬けの糠で煮たもの。甘辛味で骨まで柔らかく、ご飯がすすみます。大好物で〜す\(^o^)/ pic.twitter.com/xw3X15Rx
— 奥薗壽子 (@toshiko0813) January 5, 2012
ぬかみそ炊きは、ぬか、醤油、酒、ざらめ、しょうがなどで魚を炊く料理です。
魚は、さばやいわしなど、青魚が主に用いられます。
福岡県の郷土料理で、昔から親しまれているのだそう。
ぬかの旨みがしみ込んで、とても美味しそうです。
ごはんのお供に、酒の肴に、もってこいですね!
②古漬けの炒め物
写真忘れた❗️
古漬け炒め物 pic.twitter.com/arZUgAchYm— オバQ (@cooma823) June 20, 2021
漬かりすぎてしまった古漬けは酸っぱいですが、炒め物にすると食べやすくなります。
炒める時に油や他の具材が入ることで、古漬けの酸味が和らぐんですよ♪
いろんな具材と炒めれば、漬物の食感も加わってとても美味しくなりそうですよね。
さまざまな漬物でアレンジ無限大!
今すぐ試したくなる調理法です。
③古漬けのサラダ
レタス、わさび菜、辛いだいこん、焼きホタテ(サラダファミリー)、塩昆布、キンカン、きゅうりの古漬けのサラダ。古漬けと塩昆布の塩味が効いてるので、何もかけなくてもおいしい。 #サラダ pic.twitter.com/qnjW8Sjhwc
— 野菜を食べる翁 (@salad_okina) May 18, 2022
古漬けの酸味を活かして、サラダなどのトッピングに利用するのもおすすめ!
漬物の食感がいいアクセントになって、美味しそうですよね。
サラダの種類や漬物の種類、ドレッシングなどさまざまな組み合わせで楽しんでくださいね♪
まとめ
- ためしてガッテン流の作り方ポイントは、ぬかと塩水を混ぜること
- ぬか床の美味しさの決め手は乳酸菌
- 乳酸菌は空気を嫌うため、ぬかを混ぜすぎない
- ぬか床の適温は25度
- ぬかを食べたり古漬けを活用する方法で、無駄なく使い切れる
いかがでしたか?
今回は、ためしてガッテンで紹介された「ぬか床の作り方」をご紹介しました。
ぬか床のお手入れポイントも参考にしながら、お手製ぬか床に挑戦してみてくださいね!
そして自分が作ったぬか床で、好きな野菜を漬けてみてはいかがでしょうか♪
とはいえ、初心者が一からぬか床を作るのは大変な作業だと思います。
まずは、完成したぬか床を購入して育てていくのも良いかもしれませんね♪