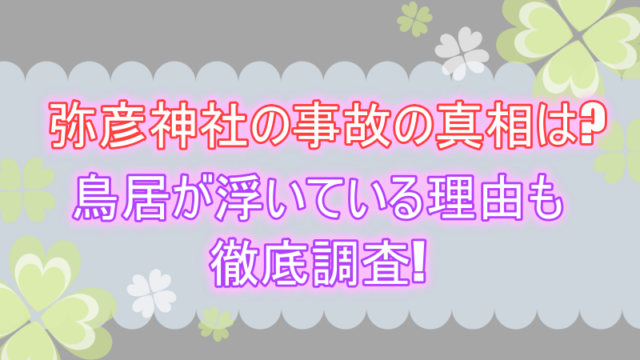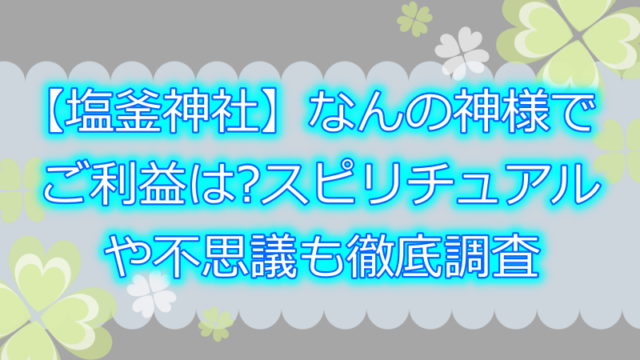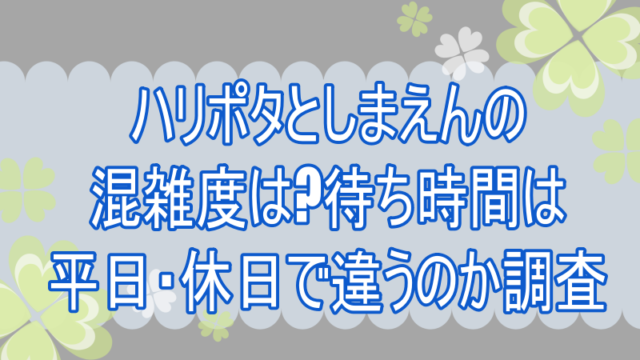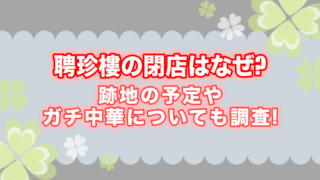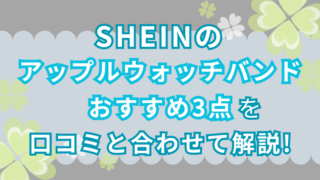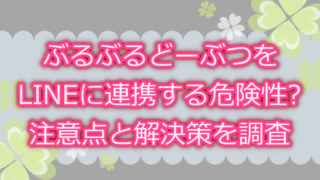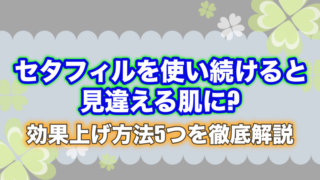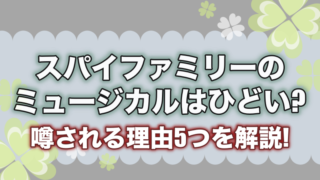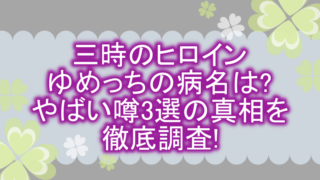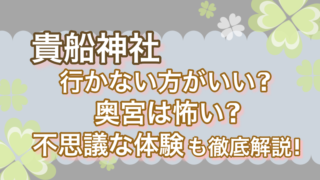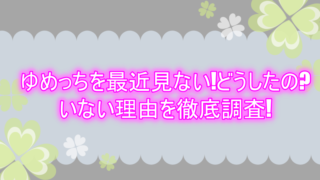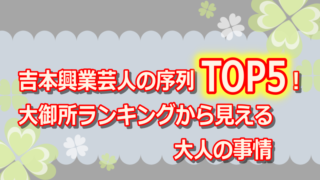近親婚の風習が残る地域は?日本の歴史で続いた2つの理由を調査!
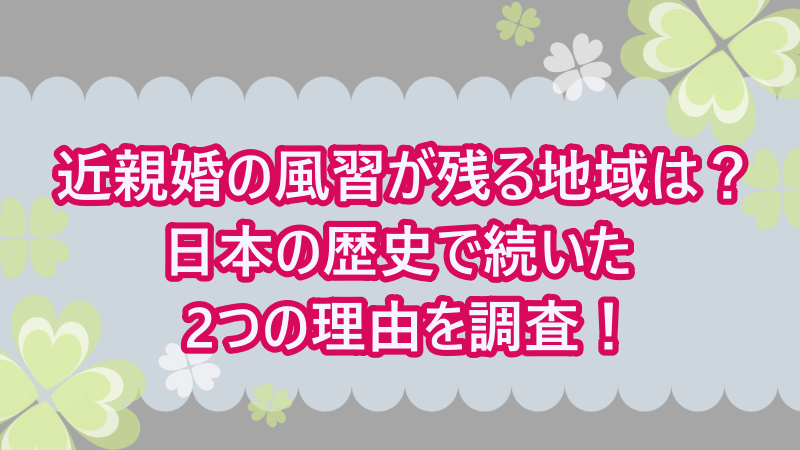
過去に各地で行われていたという近親婚の風習。
現在では一般的ではなく、倫理的・生物学的背景からもタブー視されています。
そんな近親婚の風習が残る地域は現在もあるのでしょうか?
近親婚にまつわる日本での歴史を、今回は徹底調査しました!
Contents
近親婚の風習が残る地域は?

現在では、近親婚の風習が残る地域はほぼないと言えるでしょう。
近親婚は、倫理的にも生物学的にも悪影響を及ぼすことが分かっています。
現在の近親婚率は低下中
・いとこ同士の結婚(いとこ婚率)はフランス等では常に1%を切る
・スンニ派シリア人では35%
・イラク人で36~37%
(p142)日本は?と思って調べたら、
・いとこ婚率は減少傾向、1962年以降ずっと1%未満
・近親婚率は九州で高く、北海道で低いhttps://t.co/UaoVvgK4XD— おたま@男子三児の母 (@otamashiratama) August 11, 2020
1962年以降、近親婚率は低下し続けているとのこと。
まあ、日本も戦前戦後位まで近親婚や年齢差婚はありましたからね……
うちは三代前までは近親婚でしたし— イーハトーヴォ謹製 北の塩くらげ (@saltymedusa) November 9, 2023
一方で、比較的直近まで近親婚が日本各地で繰り返されていたのも事実のようです。
特に戦前戦後は男性の人口も少なくなったことから、避けられないというのもあったのかもしれません。
1983年の近親婚に関する学術研究
また、1983年に以下の日本全国の6地域を対象に、近親婚についての調査が行われています。
- 旭川市と8町(北海道)
- 多賀城市(宮城県)
- 身延町(山梨県)
- 岡崎市(愛知県)
- 川西市(兵庫県)
- 福江市(長崎県)
この研究では、地域によって近親婚率に差があることが判明しました。
近親婚率の全国調査から、近親婚率は九州地方で高く、北海道で低いこと、また、郡部の近親婚率は市部の2倍ほど高いことが明らかにされている.
(引用:国立社会保障・人口問題研究所)
1983年の結果ではありますが、近親婚率は特に九州地方で高かったのだそう。
また、都市部に比べて地方の方が、近親婚が増える傾向にあったようです。
近親婚率が一番高いのは福江市で7.89%,次に高い値を示すのは身延町で5.53%である.一方,一番低い値は旭川地方で0.87%である.したがって,福江市の近親婚率は旭川地方の値より10倍も高いことがわかる. (引用:国立社会保障・人口問題研究所)
地域によって10倍もの差が出ることは驚きですよね…!
日本でも平家の落人伝説があるような山奥の辺鄙な田舎の排他的な村や、島、被差別部落などの特殊な地域では近親婚すすんで行われていたみたいですね。よその地域の人達と交流できないし、婚姻むすべないので。古い戸籍とりよせると、従兄弟同士の結婚が盛んに行われてた家系見つかることあります。
— 佑樹あかり (@akari_ginnji) November 9, 2023
九州地方では特に本州と離れていたことから、近親婚が進められていたと考えられるでしょう。
また、都市部に比べて人の入れ替わりの少ない地方では、近親婚をしなければ家や地域が存続できないという背景もあったのではないのでしょうか。
近親婚の風習はなぜ日本の歴史で続いた?2つの理由
日本の歴史の中で近親婚がタブーとされるようになったのは、近年であることが分かりました。
悪影響を及ぼすにも関わらず、なぜ長く近親婚が続いたのでしょうか?
それには大きく2つの理由がありました…。
- 皇族や貴族が血統や地位・権力を守るため
- 一般市民の生活や移動範囲の狭さ
それぞれの背景を、追って見ていきましょう。
1.皇族や貴族が血統や地位・権力を守るため
 1つ目は皇族や貴族など、高い身分の人々が自身の血統や地位・権力を守るためというもの。
1つ目は皇族や貴族など、高い身分の人々が自身の血統や地位・権力を守るためというもの。
日本でも古代からずっと 皇族の間で血統の純潔性を重要視するために近親婚が盛んに行われていたんですけどね〜。ちなみに現在、韓国の民法では「傍系8親等」以内の親族とは結婚できませんが、日本では4親等(いとこ)以上なら結婚できます。
— 貧民倶楽部 (@untilabequit) July 14, 2023
近親婚は劣性遺伝の顕在化リスクが経験上知られており同じ姓なら血が近いと思われたかもしれません
日本の場合は天皇家も貴族も近親婚が多かったのは家を守るためだと思います
ライバルが増え過ぎると争いになるので近親者という優位性を得るメリットがあった https://t.co/TBkptbXgVi— 菅原浩太 (@sugaharakota) May 18, 2023
自身らの持つ権力や莫大な財産を守るべく、近い血縁関係の中で婚姻を繰り返すことは最も容易な方法と言えそうです。
日本において古代から近代にかけて近親婚が続けられたという事実は、様々な文献で見つけることができます。
また、高い身分での近親婚は世界でも行われており、特にヨーロッパのハプスブルグ家の短命さは有名です。
カルロス2世はハプスブルグ家の近親婚の中でも特に度合いが高かったようで下顎前突症が特に顕著でまともにかみ合わせができなかったとのこと。
父父と母母父・フェリペ3世
父母と母母母・マルガレーテ
父母父と母父父父・カール2世
という超近親交配。
先天性の病気が複数あり38歳で亡くなっている— 茶請け (@ttensan2nd) August 30, 2022
家を長く繁栄させるための近親婚によって、家が滅んでしまうというのは当時の人にとっては想像もつかないことだったのでしょう…。
2.一般市民の生活や移動範囲の狭さ
 続いて挙げられるのが、一般市民の生活や移動範囲の狭さです。
続いて挙げられるのが、一般市民の生活や移動範囲の狭さです。
今でこそ交通機関が発達し、容易に日本全国へ行くことができますが、近年までは一般市民には難しいものでした。
先に1983年の調査結果をご紹介したように、都市部よりも地方で近親婚率が高いのもその表れでしょう。
人口が限られる中、結果として近い血縁での婚姻が繰り返されやすい環境にありました。
地域によっては近親婚が続いたことで精神疾患を発症される方も多いという研究があり、非常に根深い問題です…。
いとこ同士や、叔父と姪など近親婚の続いた家系に精神疾患を持った子孫が頻出する。
それを日本の地方で追跡調査した研究結果を読んだのだけれど…凄いとしか言いようがない😨。
「岡山県久米郡山村に於ける精神神経疾患頗度」https://t.co/TNbVbQNdUg
— ポオ🐾 (@paw_stargazer) September 2, 2023
私はじつは今ショックを受けている😿。
代々の近親婚によって母方に遺伝性の精神疾患が受け継がれているのは確かなのだが。
なんと母方の一族の村は過去に学者による学術調査が入っていた。
そして母方の一族の村は日本でも1、2を争う血族婚の地域で、精神疾患の村民の比率がハンパなかったのだ。
— ポオ🐾 (@paw_stargazer) September 3, 2023
現在は近親婚は避けられる傾向にあるので、このような事象も減っていくのではないでしょうか。
人の移動も少なく、地域や血縁間の関係が強くなっていったことで、近親婚の風習も長く残ったと言えますね…!
そもそも近親婚とは?
近親婚とは血縁関係の近い親族同士が婚姻関係を結ぶことを指します。
現在、日本の法律で認められている最も近い血縁関係での婚姻は「いとこ婚」で、それより近い血縁では法律上婚姻関係を結ぶことができません。
いとこ【従=兄=弟/従=姉=妹】 の解説
父または母の兄弟姉妹の子。おじ・おばの子。[補説]自分との年齢の上下関係や性別によって「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」などとも書く。 (引用:goo辞書)
上記解説のように、直接の血縁関係ではないものの4親等以内であることからかなり近い関係であることが分かります。
まとめ
- 年々近親婚率が低下してきており、地域として行うところもほぼないと言える。
- 1983年の研究結果では、近畿や地方での近親婚率が高かった。
- 皇族や貴族は、権力や財産を守るために近親婚を繰り返した。
- かつての一般市民は行動範囲が狭く、強い地域や血縁関係のつながりのもとに近親婚が進められた。
日本での歴史において近年まで近親婚が広く進められていたというのは、大きな驚きです。
徐々に遺伝的な悪影響が分かり、人々の生活・倫理観も大きく変わってきたことで、今ではタブー視されるのが一般的になりました。
一部の地域などでは根深い問題も起きていることから、同じ歴史を繰り返さないようにしていきたいですね。