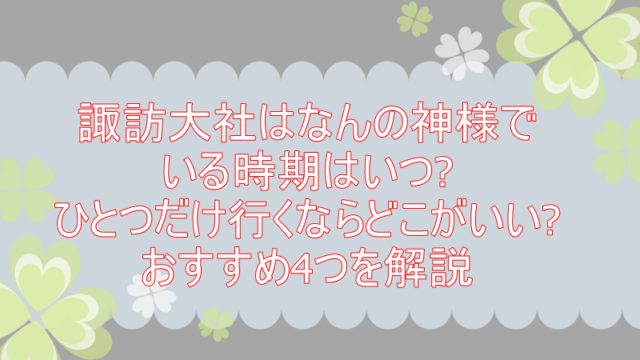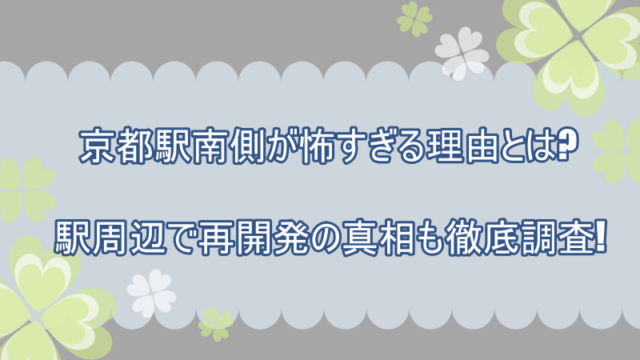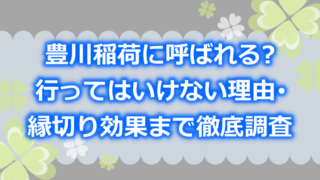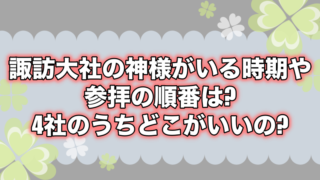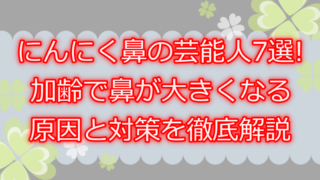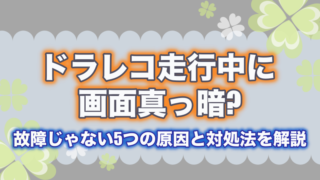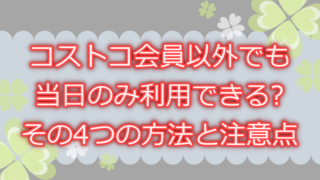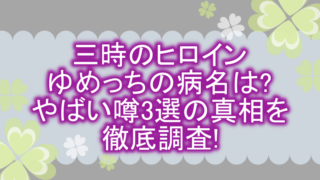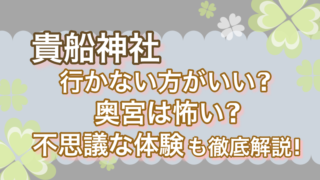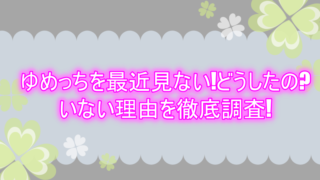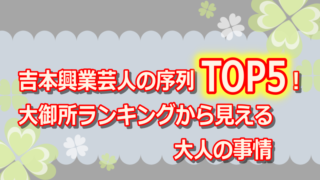【諏訪大社の怖い話】子供を生贄にしていた?呼ばれる体験談もご紹介!
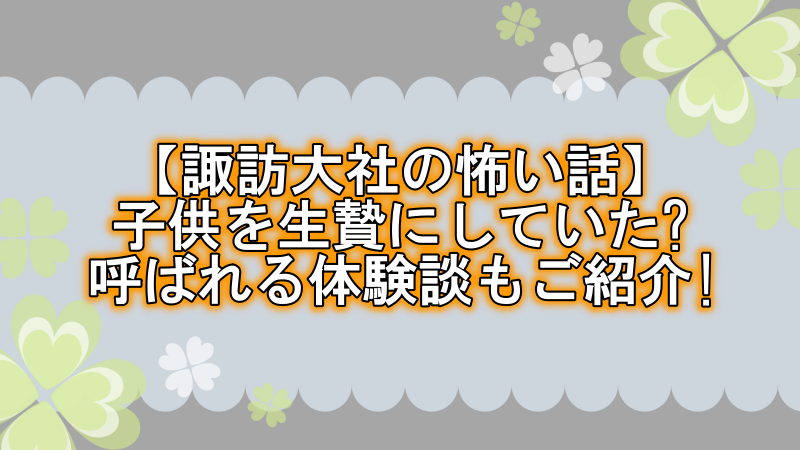
諏訪大社は、長野県の諏訪湖近くにある日本最古の神社の1つです。
この諏訪大社にまつわる怖い話をご存じでしょうか?
諏訪大社には、他の神社には見られない狩猟信仰を発祥とする独特な信仰があります。
祭祀では神様へのお供え物として、鹿や鳥などを生贄(いけにえ)に捧げる風習がありました。
一説によると「子供を生贄に捧げていた」のではないか?とのこと。
この記事では、諏訪大社にまつわる信仰と怖い話について紹介します。
ぜひ最後まで読んでみて下さい!
諏訪大社が怖いと言われる理由
 引用:諏訪市観光ガイド
引用:諏訪市観光ガイド
歴史と伝統ある諏訪大社ですが、他の神社には見られない独特の信仰でも有名です。
その異質さからか、諏訪大社にまつわる怖い話がまことしやかに語られています。
子供を生贄にしてた?
諏訪という地域は寒冷な山間部にあります。
食料が乏しかったので、古来からの狩猟文化が続いていました。
仏教伝来後も、この肉を食べる習慣は残ったようです。
「生贄の儀式」は自然の恵みに感謝するという意味で行われてきました。
【生き神としての「大祝(おおほうり)」】
最上位の役職である「大祝(おおほうり)」には、幼い男児が選ばれたと言います。
大祝となった者は、神が憑依した生き神として奉られたそうです。
神を降ろす神官と蛇形の自然神と共に、半地下の土室で冬籠りをする神事。
12月から約3ヶ月間のその「御室入り」はとても重要なものでした。
幼い子供が自分の意思で神を降ろすのではなく入れ物として使われていたそう…
「神に仕える子供」としての生涯だった…なんだか怖くて切ない話です。
- 諏訪大明神(タケミナカタ)の子孫の役割だった。
- 生き神として扱われた(神を降ろす・憑依させた)。
- 5、6歳から15、6歳まで木偶(人形)の扱いだった。
- その後は諏訪の外には出れず隠居生活となる。
- 1871年の太政官布告により神職の世襲が廃止された。
一説によると「大祝」に選ばれた子供を生贄にしていたのではないかという話も…
諏訪大社については調べると色々出てきますが、実はこれ以上記されてません。
【諏訪大社の「神使おこう」】
自然神のエネルギーを「神使(おこう)」が信濃国を巡って配る儀式。
- 江戸時代以前に行われていた儀式。
- 少年が「おこう」(御神・神使)という役割に選ばれる。
- その少年を「象徴的」に「生贄」として捧げる。
- 御贄柱(おにえはしら)に縛り、そばに小さな刃物を置く。
- 神事の後、少年は神官に解放される。
- 更に昔は人間の胎児も「生贄」として捧げたという噂もある。
【諏訪大社の「蛙狩神事(かわずがりしんじ)」】
- 毎年元旦に行われる(現在も存続している儀式)
- 国家平安と五穀豊穣の祈願。
- ご神域を流れる御手洗川の底から、冬眠していたアマガエル2匹捕らえ拝殿の前にて、矢で射抜き「生贄」として捧げる。
- その由来は諏訪大社の祭神は蛇神「ミシャクジ神」だったから。
- 動物保護団体から残虐的だと毎年抗議が殺到している。
諏訪大社の【御頭祭(おんとうさい)】
「神使(おこう)」の儀式がこの「御頭祭」に繋がる。
- 毎年4月15日に行われる。
- 現在は、鹿や猪の頭部を剥製にしたものを「生贄」としてる。
- 昔は本物の鹿の首75頭、猪の首、ウサギを串刺し、魚、雉を「生贄」にしていた。
- 神事の際、鹿の肉・脳を食べた。
諏訪信仰とは?
 引用:諏訪市観光ガイド
引用:諏訪市観光ガイド
諏訪信仰とは諏訪大社を中心に、全国に伝わっている民間信仰(ミジャクジ信仰)の事。
太古の日本で信仰されてた、古層の蛇神「ミシャグジ神」が祀られています。
本来、血の穢れが持ち込まれない聖域である神社の祭事としては、生き物を殺してお供えするという行いは異質な伝統と感じますね。
こういった土着文化は、現代から見ると怖いと感じる人も多いようです。
諏訪大社について
https://twitter.com/HJAOkUzdNPEmp8T/status/1548629989150855168?s=20&t=40Jb_uXb1tyNkPurqlJPPQ
諏訪大社は、長野県諏訪湖周辺の4つのお宮から成る神社です。
この諏訪大社を総本社として、全国各地に約1万以上の諏訪神社が点在しています。
その土地ごとに「お諏訪様」「諏訪大明神」といった愛称で親しまれ多くの人にとって身近な神社です。
諏訪神社の最上位の神職は、諏訪氏(すわうじ)が務めました。
世襲であの「大祝」を努めてきた一族です。
諏訪氏とは、諏訪大社の祭神、建御名方(たけみなかたのかみ)の末裔。
狩猟の神、水と風の守護神として古くから崇められてきました。
日本最古の神社の1つと言われており、古事記の中にも登場します。
中世の時代には、軍神として多くの武士から信仰を集めていました。
御柱祭について
 引用:諏訪大社公式サイト
引用:諏訪大社公式サイト
「御柱祭」は7年に1度「寅と申」の年に行われる日本三大奇祭として有名!
社殿や御柱を建て替えるお祭りです。
諏訪神社の御柱祭は、平安時代初期から1200年以上も続く歴史ある行事。
柱の木は樹齢200年以上の、巨大なモミの木が16本選ばれ、4つのお宮に4本ずつ運ばれます。
これらの巨木が数千人の氏子達によって担がれ、川や丘を運ばれていく様子は圧巻!
しかし…かなり危険な行事でなので、毎回死者が出ることが問題視されてます。
この投稿をInstagramで見る
諏訪大社の基本情報
- 御祭神:建御名方神(たけみなかたのかみ)
八坂刀売神(やさかとめのかみ) - 所在地:
<上社>本宮:長野県諏訪市中洲宮山1 前宮:茅野市宮川203
<下社>春宮:長野県諏訪郡下諏訪町193 秋宮:下諏訪町5828 - 付属設備開館時間:
<上社本宮宝物殿>午前9時-午後4時
<下社秋宮宝物殿>午前10時-午後3時
諏訪大社に呼ばれる体験
https://twitter.com/hu9_1201/status/1550708348068081667?s=20&t=40Jb_uXb1tyNkPurqlJPPQ
神社やお寺など神様が祭られている場所には、時として人が引き寄せられることがあります。
昔から人々の信仰を集めてきた長い歴史がある土地や、水や山といった自然に囲まれた土地では、人々に影響を与える力が強いとされています。
直感的に「呼ばれた」と感じて参拝した後に、以下のような体験をする人も多いようです。
- 新しい出会いがあった
- 仕事がうまくいった
- 新しいアイデアが浮かんできた
- 金運に恵まれた
他にも、人生の節目や転換点となるような体験をする人も多いみたい。
まとめ
以上の内容をまとめます。
- 諏訪大社は諏訪湖周辺に位置する日本最古の神社の一つ
- 諏訪地方には古来から狩猟文化があった
- 自然の恵みに感謝する意味で、生き物を殺して神に捧げる神事が行われていた
- 神職の最上位である「大祝」に選ばれた男児は、生き神として奉られた
- 一説によると、大祝に選ばれた男児を生贄に捧げていたと言われている
- 生き物を捧げる神事から派生したお祭りは、今でも諏訪大社で行われている
- 神社に「呼ばれた」と感じて参拝した後に運気が上がった体験談が多い
長い歴史の中で、土地の信仰に根差した独特の伝統が作られてきたんですね。
諏訪大社が怖いと言われるのは、生き物を生贄にする神事に怖さを感じるためでした。
この異質な雰囲気の神事が現代まで引き継がれているのは、今も昔も日本人が自然の中に神様を感じる民族だからかもしれませんね。