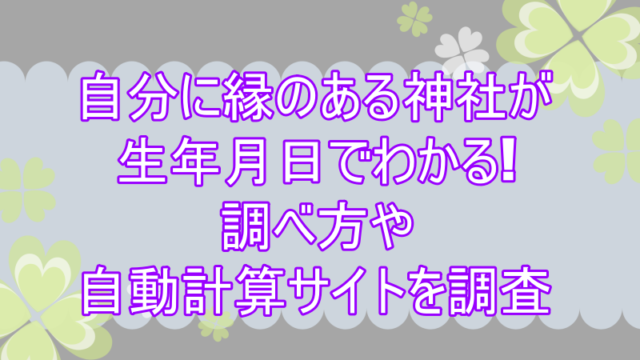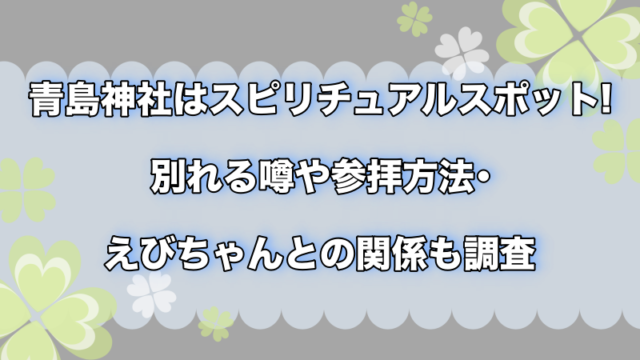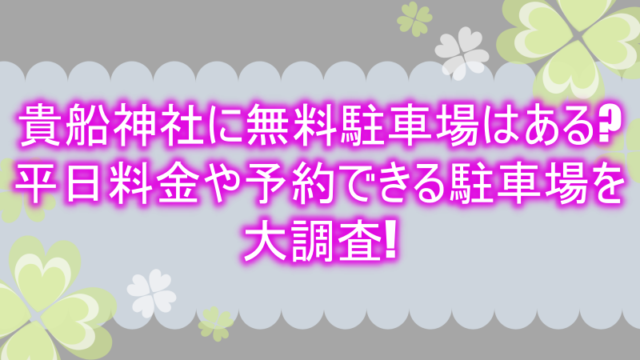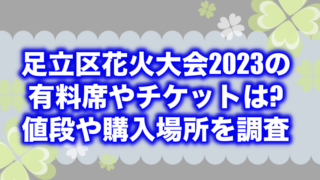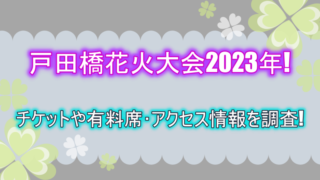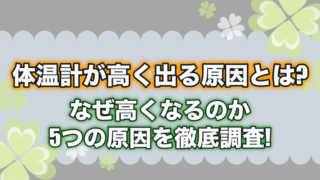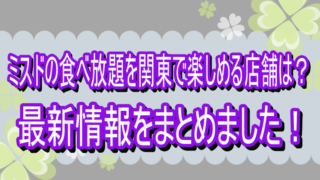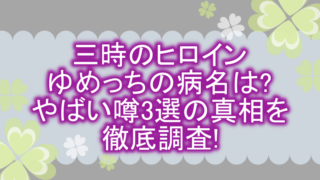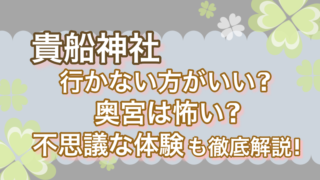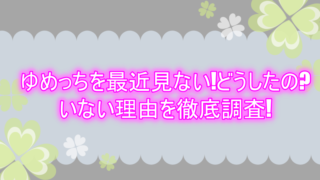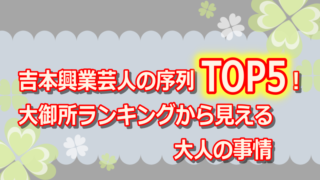弥彦神社の事故の真相は?鳥居が浮いている理由も徹底調査!
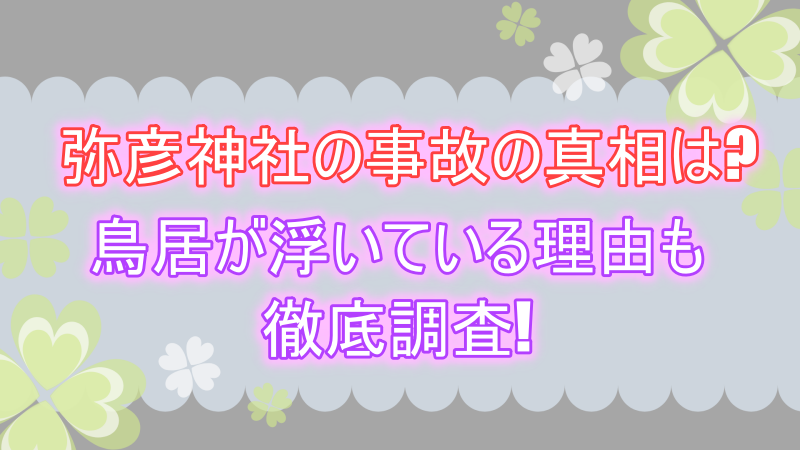
弥彦神社は、新潟県にある最も格の高い神社です。
今や、パワースポットとしても人気があります。
そんな弥彦神社ですが…
参拝客が圧死してしまった、悲しい事故が起きた場所でもあるんです。
この記事では、弥彦神社での事故の詳細、パワースポットの紹介から鳥居が浮いてる理由まで紹介していきます。
Contents
弥彦神社の事故の真相は?2つの原因を解説
1956年(昭和31年)1月1日、二年参り(大晦日の深夜0時をまたいでする初詣)に来た参拝客が、餅まきに殺到し将棋倒しになりました。
なんと死者は124名、重軽傷者80名。
明治以降最悪の群衆事故となりました。
弥彦神社は「豊作の神様」として地元民の信頼も厚く、当時約3万人が初詣に集まっていました。
そこで始まった新年を祝う「福もち」まき。
紅白の餅を拾おうと拝殿に向かう人と、参拝を終え帰る人でごった返す拝殿前。
石段で人々がぶつかり合い、身動きが取れなくなってしまいました。
人々の重みに耐えきれなくなった玉垣(神社に張りめぐされた柵)。
一気に崩れ、支えを失った参拝客が高さ3mの石垣から転落し、次々と将棋倒しになりました。
その数、ざっと200~300人。
新年を祝うために訪れた場所が、一気に悲劇の現場となってしまったのです。
血にまみれ倒れた人が次から次へと運び出されたそうです。
雑踏事故と聞いて思い出すのは、2022年にソウルで起きた雑踏事故。
この事故では、ハロウィンに集まった若者が159人亡くなりました。
その様子はSNSで拡散され、大きな悲劇として私たちの記憶に残りました。
弥彦神社での事故を映像で見ることはできませんが、惨状が目に浮かぶようですね。
事故の原因2つ
圧死事故の原因は、大きく分けて2つ。
- いつも以上に参拝者が多かった
- 神社周辺の警備の人数が少なかった
弥彦神社のある地域では、二年参りの風習があります。
元々、参拝客が集まるお正月。
しかしこの年は、人が集まる3つの条件が重なりました。
- 新潟では珍しく「雪のない年」だったこと
- 前年が豊作で経済的に余裕のある家庭が多かったこと
- バスなどの公共交通機関が大きく発達し、遠方からの参拝客が増えたこと
いつもなら多くても2万人程だった参拝客が、3万人も集まったのです。
神社は、人手が増えることを予想していました。
照明や、警備の数を前年より増やしていていたのです。
しかし、その警備の多くが交通整理に当たり、拝殿の近くにはいなかったのです。
事故のその後…
この事故を受け、神社の責任者4人が過失致死罪で逮捕されました。
また弥彦神社の正宮司・権宮司、新潟県警本部長が辞任しています。
元旦恒例だった福もちまきも、その年限りで中止。
通路や石段の拡張も行われました。
翌年の1957年からの初詣では参道が一方通行になったそうです。
多くの犠牲になった方達がいたからこそ、改善されたのですね。
 拡張された随神門前の石段
拡張された随神門前の石段
引用・弥彦神社公式ホームページ
弥彦神社の鳥居が浮いてる理由
https://twitter.com/WalkingSunGod/status/500192392935256064
一の鳥居の真ん中の柱、宙に浮いてるんです。
その隙間、約6cm。
ティッシュの箱がすっぽり入ってしまいます。
「どうやって支えているの?」とビックリですよね。
このように中央の親柱が浮いている型は、両部鳥居といいます。
両脇の稚児柱で支えるという仕組みになっているんですよ。
柱が浮いている理由は、諸説あります。
有力なのは、腐食を防ぐため。
豪雪地帯故の理由ですね。
また、地震で揺れても折れないようにという話もありますよ。
弥彦神社のパワースポット4選
新潟県随一のパワースポットとして人気のある弥彦神社。
今回は、4つご紹介します。
- 一の鳥居
- 玉の橋
- 火の玉石(別名・重軽石)
- ご神木
①一の鳥居
 引用・弥彦神社公式ホームページ
引用・弥彦神社公式ホームページ
弥彦神社の入り口に立つ朱色の「一の鳥居」。
高さ約8.5m、柱の間は約6mもある立派な鳥居です。
②玉の橋

一の鳥居をくぐってすぐ左手、御手洗川にかかる「玉の橋」。
神様だけが通ることのできる神聖な橋です。
赤く見えているのが、橋の部分。
なんとも急なアーチ、私たち人間が渡るのは無理そうですね。
この御手洗川にかかる参拝者が渡る石橋にも注目です。
 よく見てみると、継ぎ目がないんです。
よく見てみると、継ぎ目がないんです。
一枚岩で作られているそうですよ。
そこまで大きな一枚岩、探すのも運ぶのも大変そうですよね。
③火の玉石(別名・重軽石)

参道を進み、手水舎(ちょうずや)の近くにあるのが「火の玉石」です。
2つの石が並んでいて、願い事が叶うかを占ってくれます。
やり方は簡単!!
- 願い事を心に浮かべながら石を持ち上げます。
- 石が軽く持ち上げられたら→願いは叶う。
石が重く感じたら→願いを叶えるには努力が必要。
石を持ち上げるコツは、肩幅に足を広げ、腰を落として引き寄せること。
夢中になって、腰を痛めないように気をつけてくださいね。
④ご神木

手水舎の向かいにあるのが「ご神木」。
弥彦神社の御祭神「伊夜日子大神」(いやひこのおおかみ)が弥彦で神社の位置を決めようとしていた時のこと。
携えていた椎の杖を地面に突き刺したところ、その杖が大きな大樹となり弥彦神社の位置が定まったという謂れがあるそうです。
なんとも立派なご神木。
そばにいるだけで、いい力をもらえそうですね。
弥彦神社とは
 引用・弥彦神社公式ホームページ
引用・弥彦神社公式ホームページ
弥彦神社は、「おやひこさま」と呼ばれ、昔から地域の人に親しまれている神社です。
2400年以上の歴史を持ち、万葉集にも詠われています。
| 住所 | 〒959-0393 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2887-2 |
| 電話番号 | 0256-94-2001 |
| 祈祷受付時間 | 午前8時30分から午後4時まで |
| 交通アクセス | 【電車】JR弥彦線「弥彦」駅より徒歩約15分 【車】北陸自動車道「三条燕」ICより約30分、「巻潟東」ICより約30分 |
| 駐車場 | 無料駐車場有(神社脇駐車場:大型バス20台・普通車50台) 菊まつり期間中は一部有料 |
| 御祭神 | 伊夜日子大神 御名 天香山命(あめのかごやまのみこと) ※天照大神(あまてらすおおみかみ)のひ孫 |
| 御利益 | 開運・商売繁盛・病気平癒・学業成就・縁結び、ほか |
| HP | 弥彦神社公式ホームページ |
弥彦神社の参拝方法は、「二礼四拍手一礼」の作法でのお参りを推奨しているそうですよ。
弥彦神社のシンボル大鳥居
かつて日本一の高さだった弥彦神社の一の鳥居。
その後2年後大神神社の大鳥居、さらに現在最高の高さである熊野本宮大社、大斎原の大鳥居が建立され3番目になりました。30mを超える鳥居はこの3基だけ。 pic.twitter.com/uOCaHlp1a1
— 山田ごう@神社巡拝家 (@jmj_jp) May 15, 2019
弥彦神社に向かうとドンっと見えてくるのが、大鳥居。
上越新幹線開通を記念して昭和57年に建てられました。
この鳥居は、「一の鳥居」がモデルとなっているのですが、とにかく大きい!!
高さは30.16m。
7~8階建てのビルの高さに相当します。
鳥居の真ん中にある神額(しんがく)は、畳12畳分もあるそうです。
どれだけ大きいかがわかりますね。
観光客に人気の撮影スポットになっているそうです。
弥彦山山頂にある御神廟(ごしんびょう)は縁結びの名所
 引用・弥彦神社公式ホームページ
引用・弥彦神社公式ホームページ
弥彦神社の後ろにそびえ立つ弥彦山。
その山頂に御神廟(神の霊を祀ったところ)があります。
祀られているのは、彌彦神社の祭神「天香山命」と妃神「熟穂屋姫命」(うましほやひめのみこと)。
仲良く2人で祀られていることから、縁結びの名所として知られています。
カップルで行くと別れる!?という噂もあるようですが、安心してください!!
完全に否定されています。
新潟県民、特に女性の間では彌彦神社の神様「おやひこさま」が女性だという噂がささやかれています。
ですが!おやひこさまは正真正銘の“オトコ”の神様です。
なぜそんな噂が飛び交っていたのかというと?江戸時代の頃、地元の男性が温泉街へ遊びにいく際に、奥さんがついてこないように
「おやひこさまは女の神様なので、夫婦で行くとやきもちを焼く」と嘘をついたのが今に伝わっているよう。全国の温泉街にほど近いパワースポットでは似たような噂があるようですね。 引用:弥彦観光協会
恋守も弥彦神社境内の札所で手に入れることができます。
 弥彦山の標高は634m。
弥彦山の標高は634m。
あのスカイツリーと同じ高さです。
景色は360度の大パノラマ。
佐渡や越後平野、遠くは能登半島まで見渡すことができるそうですよ。
御神廟へは、ロープウェイで約5分、山頂駅から徒歩15分で行けますよ。
絶景を見に訪れてみてください。
まとめ
- 1956年の元旦に起きた圧死事故では、124人の方が亡くなった
- 事故の原因は、想定外の参拝者の多さと警備員の不足
- 事故後は石段が拡張され、参道は一方通行になった
- 一の鳥居が浮いてる理由は、腐食を防ぐためが有力
- 弥彦神社は新潟県随一のパワースポット
過去に悲しい事故のあった弥彦神社。
それでもなお、現在まで地元の信頼を得られているのは、弥彦神社の真摯な姿勢があったからなのかもしれませんね。